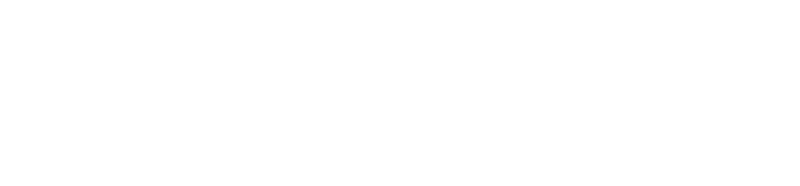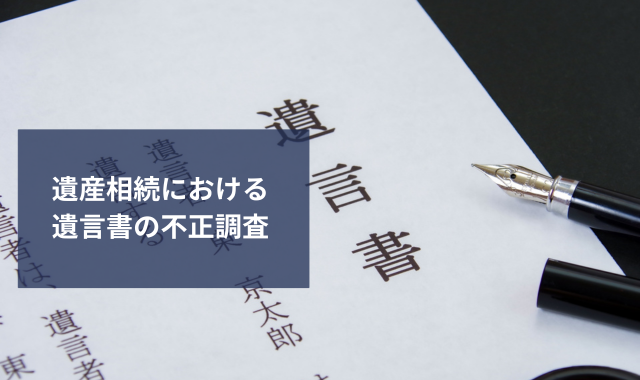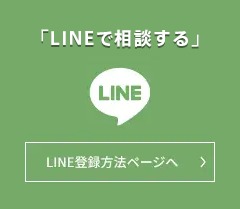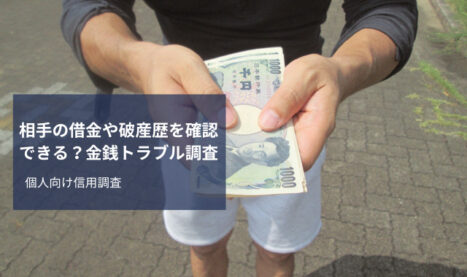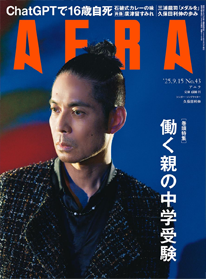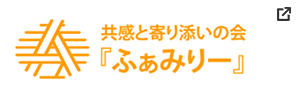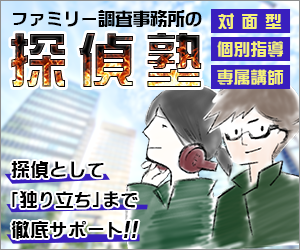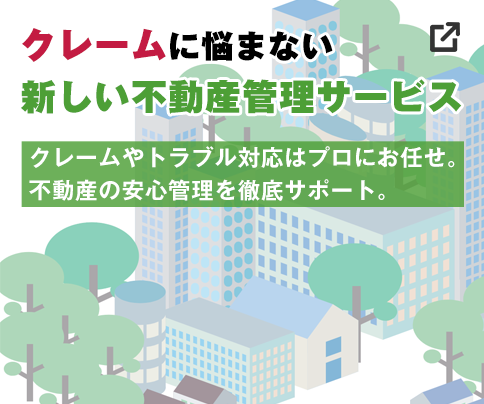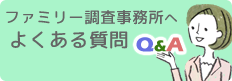相続の発生後、遺言書がトラブルの火種になる事例が少なくありません。
遺言書に関しては、法的な分野で弁護士の仕事ではないかと思われますが、不正調査や状況証拠を収集する必要がある事例が多く、証拠収集は探偵にしかできません。
この記事では、相続における遺言書トラブルに関する対処法について探偵目線で解説いたします。
相続トラブルに関するご相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
目次
裁判沙汰の相続トラブル増加
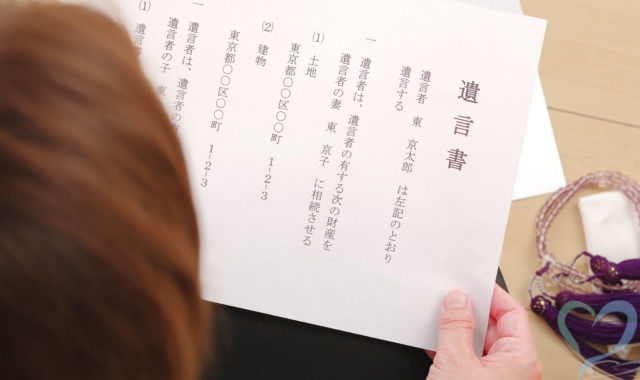
団塊世代の高齢化に伴い、相続トラブルも増加傾向にあります。
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の件数は、20年間で約128%も増加しています。
2000年 約8900件
2020年 約1万1300件
相続で揉めるのは、多額の遺産があるごく一部の人だけというイメージがあります。
しかし、実際は遺産額の大きさに関わらず相続トラブルは発生するといえます。
遺産相続を機に、家族の絆が台無しになった事例は多くみられます。
遺産相続の相談事例
遺言書の不正調査

ご依頼者は、お父様が他界された後の遺産相続において、なぜか兄弟間で大きな差があることを知ったそうです。
以前から、家族間の関係性が良くないことも影響しているのではないかということでした。
財産分配に関する遺言書作成において、何かしらの不正が行われたのではないかという疑念から探偵調査を依頼されました。
遺言書についての法的根拠

遺産相続の手続きは遺言書がある場合、遺産分割は原則として遺言通りに行われます。
遺言は民法所定の方式があり、自筆証書遺言・公正証書遺言が一般的です。
例えば、口頭で行なっても有効とはなりません。
遺言書は「自筆」が絶対条件
自筆証書遺言は遺言者が手書きで行うことが絶対条件です。
よって、代筆によって作成された遺言は、遺言者の口述を正確に筆記したとしても無効となります。
民法改正ににより、遺言書に添付する一部の書類に限定してパソコンが認められましたが、基本的には自筆が必要となります。
遺言が無効になった事例
手が震えるなどして本人が文字を書くことが困難なだったため、他人の補助を受けて書いた遺言が「無効」とされた判例があります。
印鑑の無断使用は刑事罰
遺産相続トラブルに関して、贈与契約書を偽造する悪質なやり口が存在します。
別の文書からの署名押印部分を切り貼りするケースや、本人無断の署名・印鑑の無断使用や持ち出しによる偽造があります。
こういった偽造の手口は「印鑑の冒用」とされ、刑事罰が適用される犯罪です。
遺言能力の有無
遺言をする人に「遺言能力」がなければ遺言を残すことはできません。
これについては、法的には「遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足る意思能力」とされています。
認知症などを発症していた人の場合が当てはまるかどうかの判断は、一概に「認知症=遺言書は無効」とはならないため、「遺言能力」の有無についての状況を示す証拠が必要になるケースがあります。
遺言書不正調査のポイント

遺言書が有効かどうか
相続の対象となるものには、現金、預貯金、株式などの動産から、マンションや土地などの不動産、事業継承、あるいは借金など負の遺産なども含めて多種多様にあります。
遺産相続人となった関係者にとって、遺言書はその人の生活や人生に大きな影響与える可能性があるため、慎重に公平に取り扱われる必要があります。
- 筆跡が本人のものであるか確かめる筆跡鑑定
- 遺言作成時の遺言能力の有無を含めた状況確認調査
- 共同相続人の行動調査
- 相続問題を扱う弁護士の無償紹介
- 法的措置に向けたトータルサポート
遺言書の不正の関する相談窓口

兄弟姉妹や親戚など、今まで仲が良かった間柄であっても相続問題をきっかけに関係が悪化し、骨肉の争い「争続」と呼ばれる事態に発展するケースは少なくありません。
当事務所では、相続トラブルや遺言書の不正に関するご相談をお受けしています。
まずは無料相談にてお問い合わせください。

執筆者:Rita Hayes / リタ・ヘイズ
教育業界で10年以上の経験を積んだ後、2023年4月FAM Investigation入社。海外事業部の立ち上げと責任者としての運営を担当。入社当初から、国際調査体制の構築やグローバルパートナーシップの形成に尽力し、同社の国際展開を牽引している。
専門分野は、OSINTを活用したオンライン調査、潜入、尾行、張込みなどのフィールド調査、海外調査案件のマネジメント。