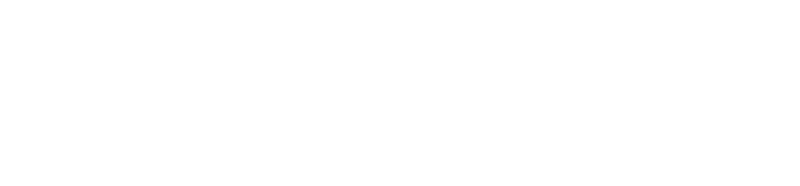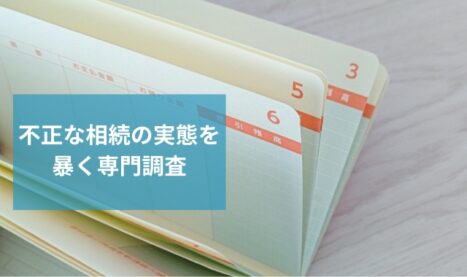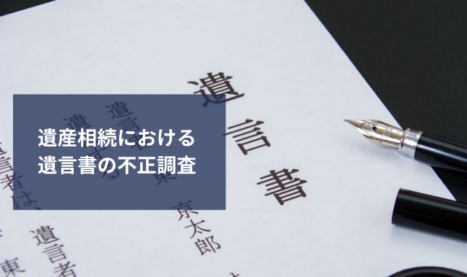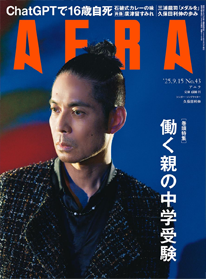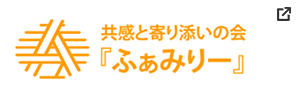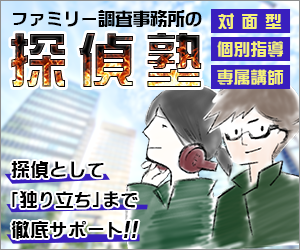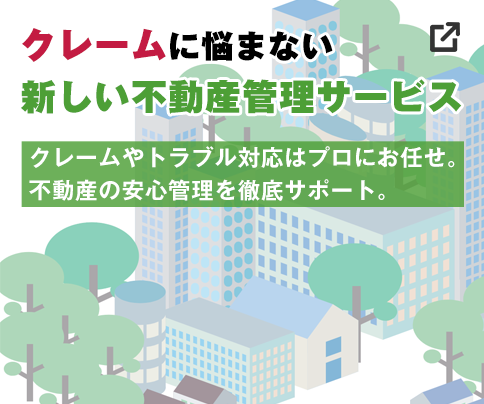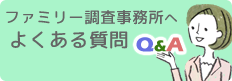亡くなった夫(被相続人)に自分の知らない子ども、いわゆる婚外子(隠し子)がいたら……。
相続手続きの最中に、このような事実に直面すると大きな不安と混乱に陥るでしょう。
「婚外子も相続人になるのか?」「どのように連絡を取ればよいのか」など、悩みはつきません。
この記事では、相続における婚外子の調査が重要な理由から、具体的な対処法まで解説します。
記事を読めば、婚外子調査の全手順から法的なリスク、具体的な解決策まで把握でき、次に何をすべきか冷静に判断できます。
目次
相続で婚外子の調査が重要となる3つの理由
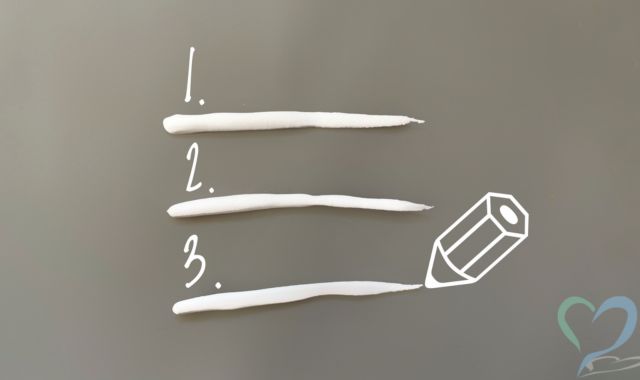
まずは、相続で婚外子の調査が重要となる3つの理由をご紹介します。
認知されていれば法定相続人として扱われるから

相続で婚外子の調査が重要となる理由は、被相続人に認知されている婚外子は結婚している夫婦間の子どもと同じ立場の法定相続人となるためです。
法定相続人とは、法律によって遺産を相続する権利が認められた人のことです。
被相続人の子どもは、誰よりも優先して遺産を相続する権利を持ちます。
婚外子であっても父親が認知さえすれば、正式な親子として扱われ、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)と同じ相続権を得られます。
これまで婚外子の相続分は嫡出子の半分とされていましたが、2013年の民法改正により婚外子と嫡出子の相続分は完全に同等になりました。
例えば、相続人が妻・長男・認知された婚外子の3人であった場合、相続分の分配は以下のようになります。
- 妻:2分の1(配偶者の法定相続分)
- 長男:4分の1(子の相続分2分の1を分割)
- 婚外子:4分の1(長男と同等の相続分)
認知された婚外子は他の相続人と同等の権利を持つため、存在を無視して相続手続きを進めるのは法的に不可能です。
適切な相続手続きを行うには、婚外子の存在を確認する必要があります。
※参考:民法第八百八十七条・第八百八十九条・第八百九十条・第九百条|e-GOV法令検索
婚外子を除いた遺産分割協議は無効になるから

婚外子を除いて行った遺産分割協議は、法的に無効となるため調査が不可欠です。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどれだけ相続するのかを法定相続人全員で話し合い、決める手続きのことです。
遺産分割協議には必ず法定相続人全員が参加し、合意しなければならないという原則があります。
一人でも法定相続人が欠けた状態で協議と合意形成を行っても、その遺産分割協議は効力を持ちません。
例えば、相続人である妻と長男が遺産分割協議を終え、被相続人の預金を解約し分配を済ませたとしましょう。
しかし、その数ヵ月後に認知された婚外子の存在が発覚した場合、過去の遺産分割協議は無効となり、ゼロからやり直さなければなりません。
過去の遺産分割協議が無効になれば、財産を婚外子に返還したり再度交渉したりする必要があり、手続き的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。
このような問題を避けるためには、相続開始時の戸籍謄本調査により認知された婚外子の存在を確実に把握することが不可欠です。
最初の段階ですべての相続人を正確に特定しておけば、有効な遺産分割協議ができ、後々のトラブルも防げます。
後から遺留分請求などの金銭トラブルに発展するから

婚外子の存在を無視して相続を進めると後から遺留分を請求され、予期せぬ金銭トラブルに発展する可能性があるため調査が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者や子、親など)に法律上保障された最低限の遺産の取り分のことです。
仮に、被相続人の遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いてあっても、法定相続人である婚外子は遺留分を主張する権利を持っており、自分の遺留分が侵害された事実を知った場合、財産を多く受け取った他の相続人に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
例えば、相続人が長男と婚外子の2人だけで、何も知らない長男が遺言書に従い被相続人の全財産1億円を相続し、その後に婚外子の存在が発覚したとしましょう。
この場合、婚外子は長男に対して2,500万円の遺留分侵害額を請求できます。
なお、遺留分を請求できる権利は、相続開始と遺留分侵害の贈与等があったことを知ったときから1年間、または相続開始から10年が経過するまで行使できます。
婚外子の存在を確認せず相続を完了させた場合、数年後に高額な金銭支払いを求められる可能性があるため事前の調査が不可欠です。
※参考:民法第千四十二条・第千四十六条・第千四十八条|e-GOV法令検索
戸籍謄本で婚外子(隠し子)の有無を調べる方法
の有無を調べる方法.jpg)
相続人調査の基本は、戸籍をたどって法的な親子関係を明らかにすることです。
ここでは、戸籍謄本で婚外子の有無を調査する手順を解説します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する
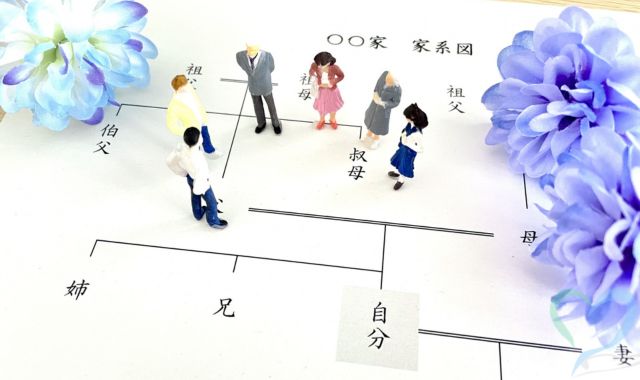
まずは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本は結婚や離婚など人生の節目、法律の改正によって新しく作られるため、被相続人死亡時の戸籍謄本だけを確認しても婚外子の有無はわかりません。
仮に、被相続人が20代の頃に子どもを認知していても、30代で再婚し新しい戸籍が作られている場合、現在の戸籍に認知の事実は記載されていないでしょう。
そのため、過去にさかのぼり、すべての戸籍謄本を確認する必要があります。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する手順は、以下のとおりです。
- 被相続人の最後の本籍地の市区町村で戸籍謄本を取得する
- 移動内容で前の本籍地を確認し、その本籍地の市区町村で戸籍謄本を取得する
- 1と2の作業を被相続人が生まれた時点の戸籍にたどり着くまで繰り返す
また、戸籍謄本を請求する際は、以下の書類や手数料が必要です。
- 戸籍謄本等の交付請求書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 被相続人との関係がわかる戸籍謄本
- 手数料(戸籍謄本および抄本:450円・除籍謄本および抄本:750円など)
婚外子の有無を正確に把握し適切な相続手続きを行うために、被相続人のすべての戸籍謄本を取得しましょう。
※参考:戸籍証明書・戸籍謄本|市川市
戸籍の身分事項欄で認知の記載を確認する

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得したら、各戸籍謄本の身分事項欄で認知に関する記載を確認しましょう。
戸籍謄本の身分事項欄には、出生・結婚・離婚・養子縁組など、個人の身分変動が記録されており、被相続人が法的に婚外子を認知していれば、その事実が以下のように記載されています。
- 認知日
- 認知した子どもの氏名
- 認知した子どもの戸籍(本籍地・母親の氏名)
この記載は、婚外子が法的な相続人であることの証拠です。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し身分事項欄を精査することで、認知した婚外子の存在を法的に確定できます。
古い手書きの戸籍謄本では文字が読みにくい場合もありますが、相続手続きにおけるトラブルを避けるためにも、すべての戸籍謄本の身分事項欄で認知の事実を確認してください。
戸籍謄本調査の限界と戸籍謄本以外の資料や情報で発覚するケースを把握する

戸籍謄本はあくまで法律上の身分関係を証明する書類であるため、記載されていない事実や情報があることを把握しておきましょう。
被相続人が子どもの存在を知っていても認知の手続きをしていなければ、その子どもは戸籍謄本に記載されないため注意が必要です。
また、戸籍謄本で確認できるのは婚外子の氏名と本籍地であり、現住所まではわかりません。
婚外子の現住所特定には別途、戸籍附票を取得する必要があります。
さらに、被相続人の死後に子どもが訴訟を起こし、裁判所の判断によって親子関係が認められる死後認知という制度もあります。
死後認知の場合、相続開始時点の戸籍謄本に認知の記載はありませんが、後から法的な相続人として婚外子が連絡してくる可能性もあるでしょう。
その場合、遺産分割協議をゼロからやり直す必要があります。
他にも、遺言書の内容や被相続人が残した手紙、親族や知人からの話など、戸籍謄本以外の資料や情報から婚外子の存在が明らかになるケースも考えられます。
婚外子の有無を正確に特定したい場合は、専門家へ依頼するのがベストです。
もし婚外子がいたら?発覚後の相続手続きとトラブル対処法

戸籍謄本調査の結果、婚外子の存在が明らかになれば心穏やかではないでしょう。
しかし、婚外子も法律で認められた相続人であるため、権利を無視することはできません。
そこでここでは、婚外子発覚後の手続きとトラブル対処法を解説します。
婚外子の法定相続分がいくらかを正確に把握する

| 相続人が妻・長男・認知された婚外子で、遺産総額が6,000万円の場合 |
| 妻の法定相続分:2分の1 | 6,000万円×2分の1=3,000万円 |
| 子ども全体の法定相続分:2分の1 | 6,000万円×2分の1=3,000万円 |
| 長男の法定相続分:4分の1 | 6,000万円×4分の1=1,500万円 |
| 婚外子の法定相続分:4分の1 |
相続争いを避けるためにも、婚外子の法定相続分がいくらになるのか正確に把握しましょう。
※参考:相続人の範囲と法定相続分|国税庁
婚外子を含めた遺産分割協議を円滑に進める

婚外子の法定相続分を把握したら、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
感情論ではなく、法律と客観的事実にもとづいて遺産分割協議を進めましょう。
これにより、相続人全員が納得できる遺産分割協議が可能になり、紛争リスクを最小化できます。
また、婚外子と連絡を取る際は、手紙などでていねいかつ誠実に相続発生の事実と、今後の手続きについて協力をお願いしたい旨を伝えます。
突然の訪問や電話は、婚外子に警戒心を与えてしまう場合があるため避けたほうが無難です。
当事者同士での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停制度を利用したり弁護士や司法書士などの専門家に間に入ってもらったりするのもおすすめです。
遺留分を請求された場合の対処法を知っておく

遺言書の内容によって婚外子の取り分が法定相続分より少なくなった場合、遺留分を請求される可能性があるため対処法を把握しておきましょう。
万が一、婚外子から内容証明郵便で遺留分侵害請求の通知が届いた場合は、請求金額が法的に適切な遺留分額か確認します。
請求額が正当で支払う意思があれば、支払い方法や期限などを話し合い、合意内容をまとめた合意書を作成しておきましょう。
合意書を作成すれば、法的紛争の回避や後々のトラブルを防止できます。
ただし、遺留分侵害請求額が適切かどうかを判断するのは難しいため、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。
婚外子など全相続人の調査は必須!借金有無の信用調査も忘れずに

相続では被相続人の財産だけでなく、借金も引き継ぎます。
そのため、婚外子などすべての相続人調査は必須ですが、相続財産に隠れた借金がないか信用調査を行うことも大切です。
ここでは、相続における財産調査の基本や信用調査の方法、借金が多いときの法的手段を解説します。
相続財産の全体像を把握する

円滑かつ公正な相続手続きを進めるために、まずは相続財産の全体像を把握しましょう。
相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなくローンや借金、連帯保証人としての地位などマイナスの財産も含まれます。
相続人はこれらすべてを包括的に承継するため、プラスの財産が1億円あってもマイナスの財産が1億2,000万円あれば、結果的に2,000万円の負債を背負うことになります。
以下の財産をすべてリストアップし、評価額を算出しましょう。
| プラスの財産例 | マイナスの財産例 |
|
|
土地や建物は固定資産税納税通知書や課税明細書、預貯金は通帳や証書、株式や投資信託は取引報告書で確認できます。
未払いの税金や保険料は、市区町村や税務署などから届く督促状や催告書などで把握できます。
住宅ローンや自動車ローンなどのマイナス財産の確認方法は、次に解説しますのでこのままお読みください。
※参考:第1編第2章第2節督促|国税庁
信用調査(JICC・CIC・KSC)で隠れた借金を調査する
で隠れた借金を調査する.jpg)
被相続人の借入状況を把握するためには、信用情報機関(JICC・CIC・KSC)への信用情報の開示請求を行う必要があります。
信用情報機関とは、ローンやクレジットカードの契約内容、支払い状況などの信用情報を金融機関から集めて管理している第三者機関のことです。
被相続人の自宅に請求書や契約書がなくても、信用情報機関に照会すれば、隠れた借金や保証契約を発見できる可能性が高まります。
日本には主に以下3つの信用情報機関があり、それぞれ加盟している金融機関の種類が異なるため、可能な限りすべての機関に開示請求を行いましょう。
| 信用情報機関 | 保有している主な情報 | 公式サイト |
| 株式会社日本信用情報機構 | 消費者金融系 | JICC |
| 株式会社シー・アイ・シー | クレジットカード会社や信販系 | CIC |
| 全国銀行個人信用情報センター | 銀行や信用金庫などの金融機関系 | KSC |
開示請求には、被相続人死亡の事実が記載された戸籍謄本や請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本、本人確認書類などが必要です。
ただし、個人間の借金は信用情報機関に記載されないため、郵便物や契約書などで確認してください。
借金が多い場合の最終手段「相続放棄」の流れを理解しておく
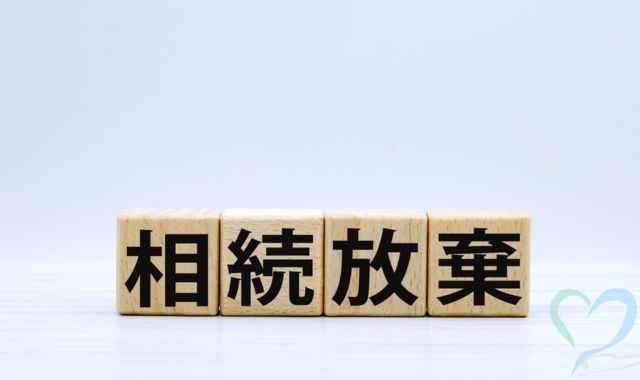
財産調査や信用調査の結果、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いと判明した場合は、相続放棄をすることで借金引き継ぎから逃れられます。
相続放棄とは、相続人としての地位を完全に放棄する制度のことです。
相続放棄が認められれば、被相続人の資産も負債も一切引き継ぐ必要がなくなります。
手続きの手順は、以下のとおりです。
| 手順 | 詳細 |
| ①必要書類を集める |
|
| ②家庭裁判所に申し立てる | 被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出する |
| ③照会書を返送する | 家庭裁判所から「本当に相続放棄しますか?」という内容の照会書が届くので、質問に答えて返送する |
| ④相続放棄が認められる | 問題がなければ家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く |
相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てる必要があるため注意が必要です。
3ヵ月を過ぎてしまうと相続放棄ができず、すべての財産と負債を相続する単純承認をしたとみなされる可能性があります。
なお、相続放棄は原則取り消せないため、慎重に検討してください。
※参考:民法第九百十五条・第九百十九条・第九百二十一条二項|e-GOV法令検索
婚外子の所在や信用調査を探偵に依頼するメリット

戸籍謄本で婚外子の存在がわかっても「見ず知らずの相手とどのように接触し、話し合いを進めればよいのかわからない」と、不安を抱いている方も多いでしょう。
このようなデリケートかつ複雑な問題は、探偵に依頼するのがおすすめです。
ここでは、婚外子の所在や信用調査を探偵に依頼するメリットをご紹介します。
戸籍謄本ではわからない現在の住所を特定できる

探偵に調査を依頼すれば、戸籍謄本や住民票では把握できない婚外子の現在の居住地を特定できます。
相続において婚外子の居場所を確認する場合、生まれてから十数年経過しているケースが多く、複数回の転居が行われている可能性が高いでしょう。
そのため、戸籍の附票で住所の履歴を追っても転居届が出されていなければ追跡が途絶えてしまう場合があります。
また、本籍地の変更や結婚により新しい戸籍が作られた場合、それ以前の住所履歴がわからなくなることもあります。
このような状況から婚外子の現在の住所を特定するには、戸籍調査だけでは不十分なことが多く、探偵による専門的な調査が必要です。
探偵は張り込みや聞き込みなど独自の情報網を活用して、公的書類では追跡できない現在の居住地を特定できます。
事前に人柄や生活状況を把握でき交渉リスクを回避できる

探偵に依頼すれば、事前に婚外子の人柄や生活状況を把握でき、交渉におけるトラブルのリスクを回避できます。
婚外子がどのような人物か知らないまま交渉に臨むと、感情的な対立を招いたり法外な金銭を要求されたりする危険性があるでしょう。
探偵による信用調査では、婚外子の人柄や経済状況、家族関係などを把握できます。
例えば、婚外子の自宅の近隣住民から「仕事に行っているようには見えない」といった情報や友人から「貸したお金を返さない」「気配りができ優しい性格」などのリアルな評価を得られます。
その結果「穏やかな人柄なので、まずは手紙で連絡するのが妥当」「経済的に困窮している様子なので、弁護士を介して慎重に交渉を進めた方がよい」など、具体的な戦略を立てることが可能です。
事前に得られる情報により、婚外子との交渉において適切なアプローチ方法を選択でき、トラブルを未然に防げるでしょう。
時間的・精神的な負担が軽減され、冷静な判断ができる

探偵に調査を依頼すれば、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。
被相続人の死を悲しむなかで突然発覚した婚外子の調査をご自身で行うことは、被相続人の知らない一面と向き合う精神的なストレスと、不慣れな調査活動に費やす膨大な時間という二重の負担を強いられるでしょう。
探偵にすべての調査を任せれば、ご自身は弁護士との法的な打ち合わせや他の相続人との対話など、当事者にしかできない重要な役割に集中する時間が持てます。
また、多くの探偵事務所では相続問題に関する調査結果を最終着地点とせず、結果をもとにその後の選択肢についても依頼者の気持ちに寄り添ってアドバイスしています。
探偵への依頼により、時間的・精神的な負担が軽減され、冷静な判断ができる環境を整えられるでしょう。
相続問題に詳しい探偵事務所に依頼すれば、弁護士との連携サポートも行ってくれるので、調査から解決まで一貫したサポートを受けられます。
まとめ

認知された婚外子は法的な相続人であり、存在を無視した遺産分割協議は無効になるだけでなく、後から相続分に相当する価額の支払いを請求されるといった深刻な金銭トラブルに発展するリスクがあります。
ご自身で調査を進める場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべてたどり、被相続人が持つ財産や負債のすべてを把握したうえで、遺産を相続もしくは放棄するかを決定します。
万が一、負債が超過している場合は相続放棄を行うことで借金を引き継がずに済みますが、相続放棄は原則相続開始から3ヵ月以内に手続きを行う必要があるため注意が必要になります。
婚外子の存在が確定した後は、感情的にならず法的な相続分を冷静に話し合うことが大切です。
しかし、これらの手続きは法的な知識だけでなく精神的に大きな負担がかかります。
もし「婚外子の所在がわからない」「見ず知らずの相手とどう接すればよいか不安」といった問題に直面しているのであれば、どうか一人で悩まずファミリー調査事務所にご相談ください。
ファミリー調査事務所では、相続に関わる調査のご相談を承っており、調査結果を最終着地点とせず、結果をもとにその後の選択肢についてもご依頼者の気持ちに寄り添ってアドバイスします。
ご希望に応じて弁護士への連携も行っており、24時間、電話・メール・LINEでご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
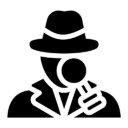
執筆者:米良
長年の情報収集経験を有し、英語での情報分析も得意とする。豊富な海外調査実績をもとに、国内外の問題を独自の視点で解説します。