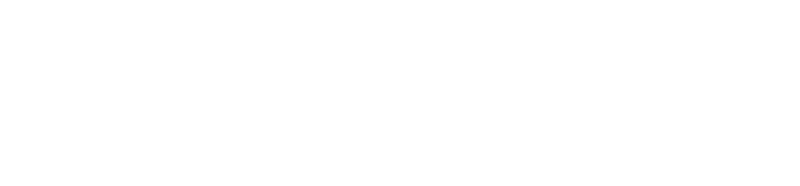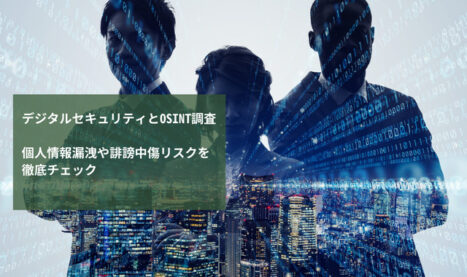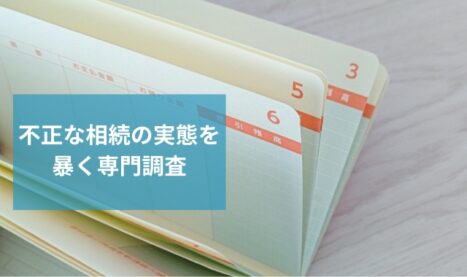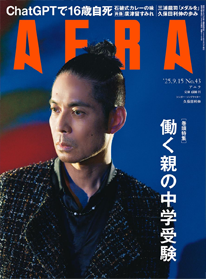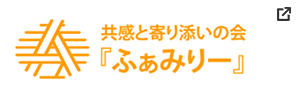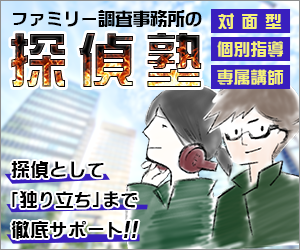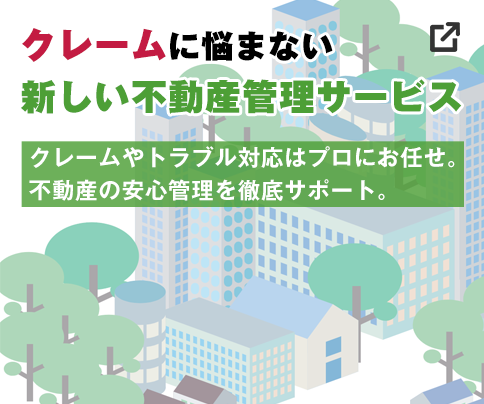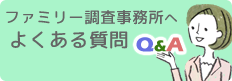PCの修理を手掛ける日本PCサービス株式会社によると、デジタル遺品に関する相談件数は、この約10年で1.6倍になったようです。
スマホやPCが必需品になった現在では、今後も相談件数の増加は続き、デジタル遺品に関するトラブルはさらに増加することも予測されています。
デジタル遺品とは、被相続人が残したスマホやPC内のデジタル機器やクラウド上に保存されたデータやSNSアカウント、暗号資産など形のない遺品のことです。
今回の記事では、デジタル遺品の概要や放置した場合のリスク、確認方法などについて解説します。
目次
スマホ・PC・クラウドに残るデジタル遺品とは?

デジタル遺品とは被相続人が残したスマホやPC内に残るデータのことです。
その他の遺品とは異なる点もあり、近年トラブルを引き起こしています。
ここでは、デジタル遺品の概要について解説します。
デジタル遺品とは被相続人が残したデジタルデータのこと

デジタル遺品とは、被相続人が残したすべてのデジタルデータや資産を指します。
スマホやPCに保存された写真、動画、文書から、SNSアカウント、電子マネー、暗号資産など全てのデータが含まれます。
デジタル遺品は、故人の思い出が詰まった貴重な情報であると同時に、金銭的な価値を持つものでもあるのです。
スマホやPCが私たちの生活に欠かせない存在となったことにより、相続においてデジタル遺品は身近なものになっています。
通常の遺品との違いは物理的な形があるかどうか

デジタル遺品の最大の特徴は物理的な形を持たない点です。
不動産や現金など通常の遺産と異なり、データなどの形で存在しています。
物理的な形を持たないため一見すると軽視されることもあります。
実際には、被相続人の金融資産やプライバシーに関わるデータが含まれ、相続や取り扱いには細心の注意を必要とします。
被相続人のデジタル遺品の有無を確認する方法
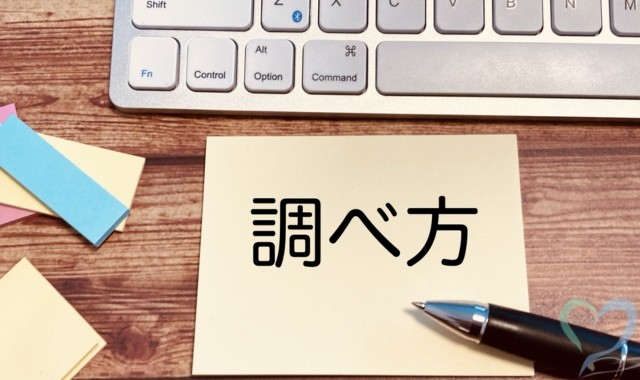
デジタル遺品は形がなかったり、被相続人にしかわからない形で保存されているので、確認の方法が難しいのが実情です。
ここでは、被相続人のデジタル遺品の有無を確認する方法を解説します。
端末のロックを解除し確認する

デジタル遺品の調査には、スマホやPCなどの端末のロック解除し端末を確認することが不可欠です。
パスワードが不明で端末が確認できない場合は、専門の業者に調査を依頼するようにしましょう。
アプリやブックマークされているサイトを確認する

被相続人のデジタル端末をロック解除できた場合、インストールされているアプリやブラウザにブックマークされているサイトを確認しましょう。
金融関連のアプリやクラウドサービス、SNSなどがあることを確認できれば、利用していたことを推測できます。
アプリの利用履歴や通知から、資産が把握できるケースもあります。
被相続人のメールを確認する

メールアカウントには、金融機関との取引履歴や契約情報、履歴の情報が残されている可能性が高いです。
ただ、メールアカウントの確認には、被相続人のプライバシーへの配慮が求められます。
クレジットカードや銀行の取引明細を確認する

クレジットカードや銀行の利用履歴から、サブスクサービスや定期的な支払いを特定できます。
解約していない契約や自動更新されるサービスの発見に有効です。
ただし、利用履歴の照会には、相続人であることを証明する書類の提出が必要です。
専門業者にデジタル遺品の調査を依頼する

専門業者に調査を依頼すれば、より詳細なデジタル遺品の調査が可能です。
上記方法を試しても、デジタル遺品の有無が全くわからなかった場合に有効です。
パスワードの解析から、データ復旧まで依頼できます。
デジタル遺品の相続人になったらすべきこと

デジタル遺品には、価値のあるものやマイナスの財産になるものがあります。
また、形がなくても通常の資産とみなされ、通常の相続の手続きを踏む必要があります。
初動を見誤ると、予期しない損失を被りかねません。
ここでは、デジタル遺品の相続人になったらすべきことについて解説しました。
デジタル遺品の相続税評価額を調べる

デジタル遺品の相続税評価額は、相続開始時点での市場価値にもとづいて算出されます。
そのため相続する際は、そのデジタル遺品の評価額を、まず把握しましょう。
オンラインバンクであれば相続開始時点での残高が評価額となり、暗号資産であれば相続開始時の価値が評価額となります。
各会社に問い合わせれば、報告書を作成してくれることもあるので相談することをおすすめします。
マイナスの財産は相続放棄を検討する
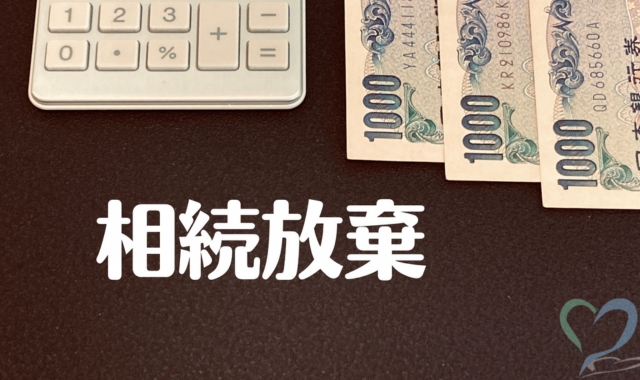
マイナスの財産が判明している場合は、相続放棄も検討しましょう。
例えば、被相続人が証券や仮想通貨などでレバレッジ取引をしていた場合、状況によっては大きな損失を出している場合もあります。
レバレッジ取引とは少額の証拠金で大きな金額を動かすことができる取引のことです。
レバレッジ取引は、少ない資金で大きな利益を狙うことができますが、その分損失も大きくなる可能性もあります。
被相続人が大きな損失を出している状況で、デジタル遺品を相続すると、マイナスの資産を相続することになりかねません。
ただ、相続放棄の期間は被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月です。
期限が過ぎたら、相続放棄することはできないので
契約サービスを解約か名義変更する
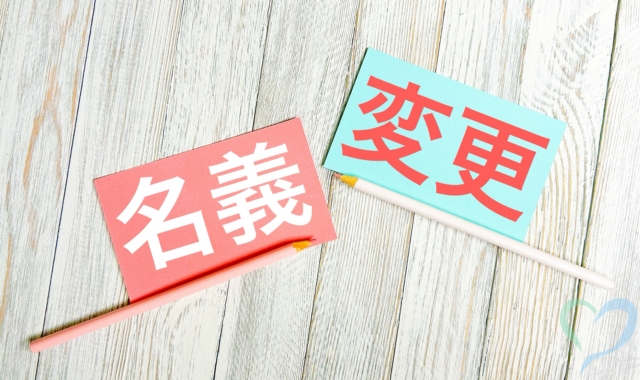
被相続人が契約していたデジタルサービスは速やかに解約または名義変更の手続きを行いましょう。
放置すると不要な料金が発生し続けることになります。
各サービス提供会社に死亡届と相続人であることを証明する書類を提出しが必要な場合があります。
ほとんどのサービスには、死亡時の解約手続きに関するガイドラインを設けられています。
解約・名義変更手続きを行えば、余分な支出を防げます。
スマホやPC内のデジタル遺品を放置するリスク

スマホやPC内のデジタル遺品を放置するとリスクがあります。
そのリスクには金銭的な損失を被ってしまい生活に影響するものも少なくありません。
ここでは、デジタル遺品を放置するリスクについて解説します。
スマホやPC内の重要なデータにアクセス不可
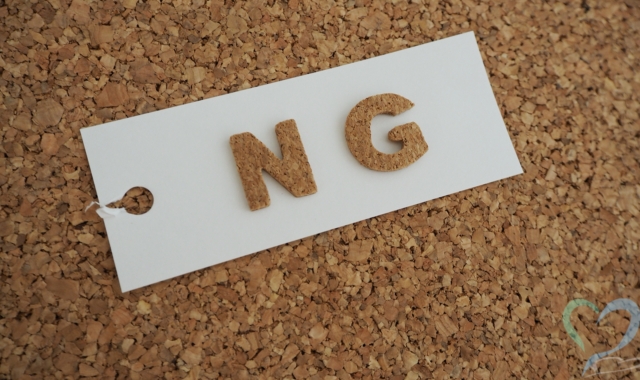
デジタル遺品を確認できない場合、被相続人の私的なものだけでなく、仕事や生活に関する重要なデータも確認できません。
現在、スマホやPCなどのデジタル端末を使わずに仕事や生活している人は少ないでしょう。
そのため、端末などの遺品が確認できない場合、仕事の引き継ぎや、生活にも影響がでます。
前述のとおり、ロック解除ができない場合は、専門の業者に依頼して端末のロック解除を依頼しましょう。
SNSアカウントが不正利用される

デジタル遺品にはSNSアカウントも含まれます。
被相続人のSNSアカウントは日常的に使用されなくなるため、不正利用されやすくなります。
不正利用されると、なりすましや個人情報の漏洩などのトラブルが発生する可能性があります。
そのため、被相続人のSNSアカウントは、追悼アカウントへの変更や削除など適切な処置を実施しましょう。
スマホ内のデータが削除される

設定によっては、誤ったパスワードを何度も入力するとスマホが初期化され、データが削除されてしまう可能性があります。
誤った操作により、貴重なデータが失われることになります。
そのため、早急にスマホ内のデータにアクセスできるようにして、バックアップするようにしましょう。
長期間放置すると故障して使用できなくなる

スマホやPCなどのデジタル端末は、長期間の未使用しないことにより、バッテリーの劣化やシステムの不具合が発生する可能性があります。
当然ですが、不具合が発生して電源がつかなくなると、デジタル遺品を確認できません。
定期的な起動やバッテリー管理など、適切なメンテナンスを知るようにしましょう。
サブスクを解約できず費用がかかり続ける

被相続人が契約していたサブスクサービスを解約せずにいると、契約が自動的に更新され、費用が発生します。
解約手続きを怠ると、会費が請求され続けるので、早めの対応が重要です。
契約状況を確認し、不要なサービスは解約しましょう。
デジタル遺品の価値が下がる

相続税評価額は相続開始時点での時価が基準です。
デジタル遺品を相続するタイミングが後になるので、場合によっては評価額と相続評価額に差が生じます。
上がった場合はいいですが、価値が下がってしまう相続する遺産に価値が低くなる可能性があります。
例えば、証券や仮想通貨、FXなどは、相続時の価値が高くても、時間とともに価値が減少することもあります。
価格変動のリスクを理解した上で、適切な時期に売却などを検討しましょう。
価格変動のリスクが高いとされているデジタル遺品は下記のとおりです。
- 証券
- 仮想通貨
- FX
- ホームページのドメイン
- SNSのアカウントなど
被相続人の知人や友人に連絡ができない

現在、知人や友人の連絡先をスマホやPC以外で管理しているという方は少ないのではないでしょうか。
被相続人が亡くなり、スマホやPCを確認できないと、連絡できません。
被相続人が亡くなったことを伝えられなかったり、大切なお葬式にも呼べなかったりということにもなりかねません。
実際、端末のロックが解除できず、被相続人の知人や友人を呼ぶことが難しかったというケースも増えているようです。
デジタル遺品の気を付ける点と知るべきこと
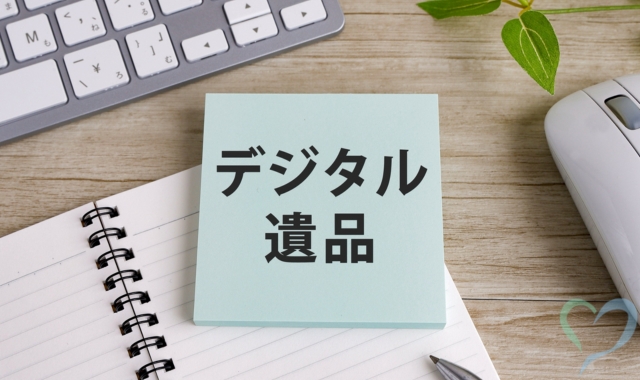
デジタル遺品の取り扱いや相続においては、気を付ける点と知るべきことがあります。
ここでは、その点について説明します。
デジタル遺品の売却・処分は相続人全員の同意を得る必要がある

デジタル遺品の処分や移転には原則として相続人全員の同意が必要です。
一部の相続人による独断は、後々のトラブルの原因となります。
相続人間で話し合いを持ち、デジタル遺品の取扱方針を決定することが望ましいです。
デジタル遺品を売却・処分するのであれば、相続人全員が同意してからにしましょう。
遺産相続の再申告が必要になる場合がある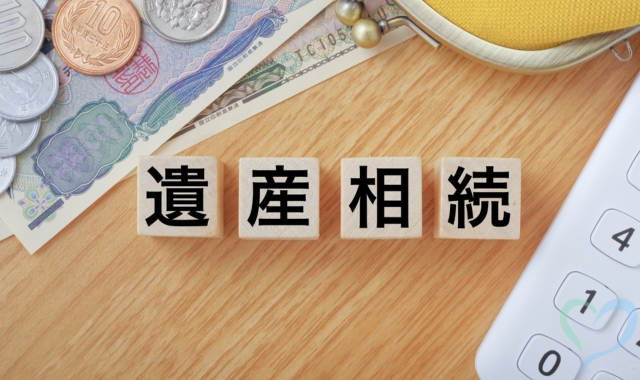
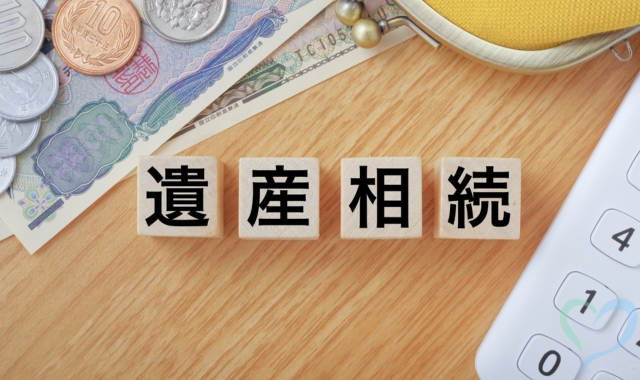
デジタル遺品の発見が相続税申告後になった場合、修正申告が必要となります。
新たに確認された資産は追加で申告しなければならず、法律に則って適切な対応をする必要があります。
仮想通貨や電子マネーなどのデジタル遺品は、特に見落とされがちな資産です。
本人以外の使用は認めないものもある
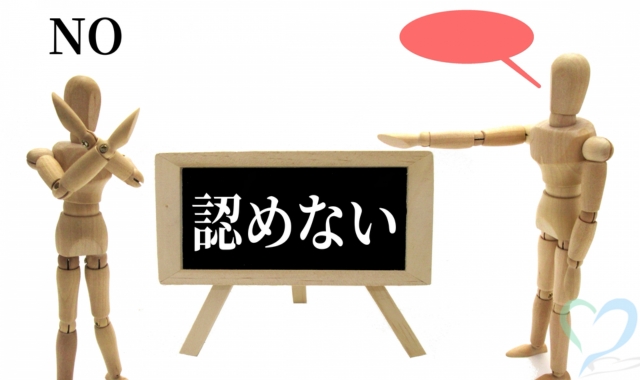
お店を使用した場合にためられるポイントもデジタル遺品です。
各種ポイントは、利用規約で相続や譲渡を禁止しているものもあり、無効になるケースや、換金・譲渡ができないものも存在します。
各サービス提供会社の規約を確認し、利用可能なポイントと失効するポイントを明確にしましょう。
デジタル遺品を相続するときの手順

デジタル遺品を相続手続きは、その他の遺産を相続する場合と基本的には変わりません。
具体的には下記のような手順で実施されます。
- 遺言状の有無、内容を確認する
- 相続人を確認する
- デジタル遺品の評価額を確認する
- 遺産分割協議を実施する
- 相続したデジタル遺品の名義変更する
- 相続税を申告後、納める
上記の手順でデジタル遺品の相続を進めれば、後にトラブルになることも少ないでしょう。
手続きに不備がある場合、ペナルティとして相続税の追徴課税をうけることもあります。
詳しくわからない場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
ファミリー調査事務所のスマホ・PC内のデジタル遺品調査

ファミリー調査事務所では、被相続人のスマートフォンやPC内のデジタル遺品調査をうけたまわっています。
当社が提供する遺品調査は、PCやスマホのデジタルデータを調査し、相続手続きを円滑に進るのをサポートするものです。
安全な方法で被相続人のプライバシーに配慮し、相続人にとって最適な解決策を提案します。
調査経験にある当事務所に依頼すれば、デジタル遺品整理のストレスを軽減できるでしょう。
パスワードが不明な場合でも、データの抽出や復旧が可能です。
スマホやPC内のデジタル遺品の調査に関するよくある質問
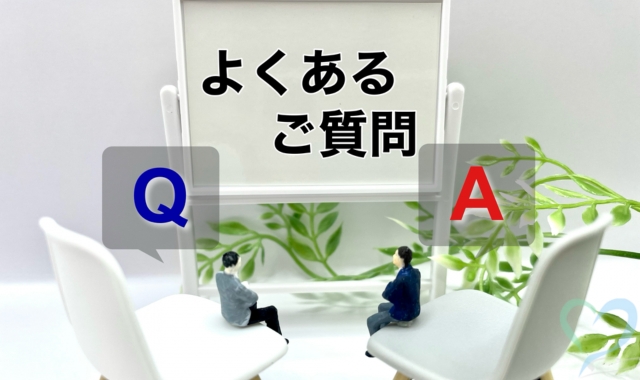
Q.デジタル遺品の種類には、どんなものがありますか?

A.写真、動画、メール、SNSアカウント、オンラインバンクの残高、クラウド上に保存されたデータ、仮想通貨、ポイントやマイレージなどがあてはまります。
Q.デジタル遺品の調査では、被相続人のプライバシーは守られますか?

A.調査は、被相続人のプライバシー保護が最優先されます。
調査員には守秘義務が課され、調査過程で知り得た個人情報は管理されます。
調査範囲は相続に必要な情報に限定され、私的なデータは相続人の意向に沿って適切に処理されます。
Q.スマホやPCなどのデジタル端末のデジタル遺品調査に必要な期間はどのくらいですか?

A.調査内容やデータ量によって異なりますが、通常では数日から数週間程度必要です。
面談時にデジタル遺品の詳細をお伝えいただければ、必要な期間をお知らせします。
スマホやPC内に残るデジタル遺品調査ならファミリー調査事務所へご相談を!

被相続人のスマホやPCに保存された情報は、個人の思い出だけでなく、重要な資産管理や法的な義務にも関わることがあります。
デジタル遺品は通常の財産とは異なり、形がないため、相続や管理においてさまざまな問題が生じます。
そのため、デジタル遺品の調査することは、デジタル遺品の相続の第一歩です。
ファミリー調査事務所などの専門家を活用することで、デジタル遺品の把握できます。
被相続人のデジタル遺品を調査する場合は、ご連絡ください。
経験ある相談員が対応します。
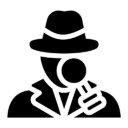
執筆者:米良
長年の情報収集経験を有し、英語での情報分析も得意とする。豊富な海外調査実績をもとに、国内外の問題を独自の視点で解説します。