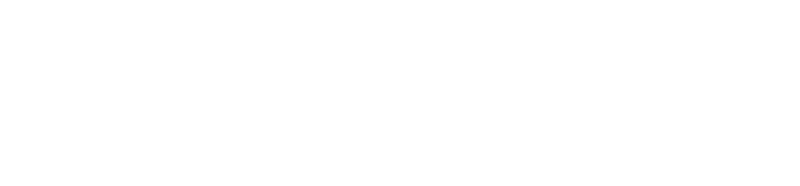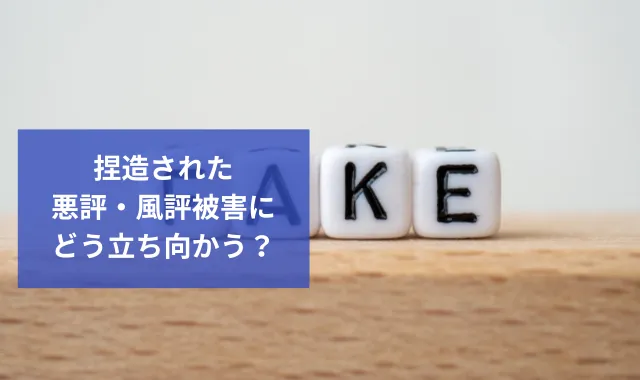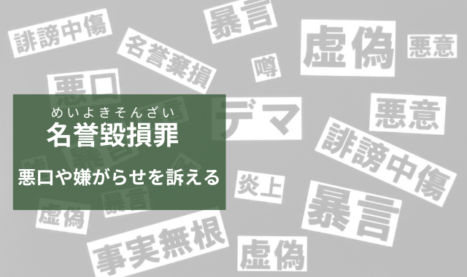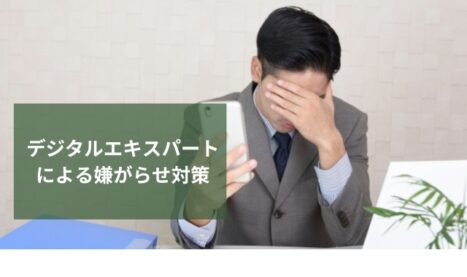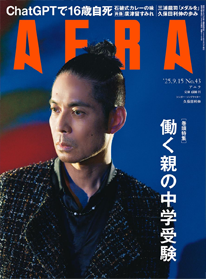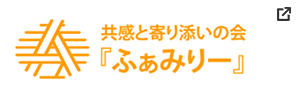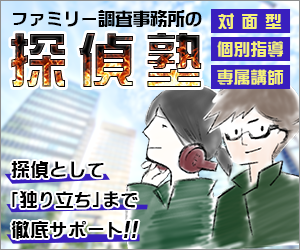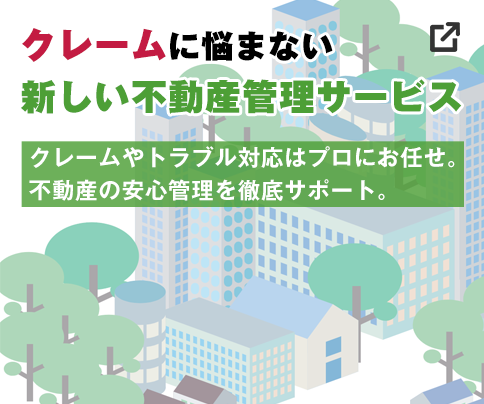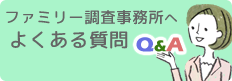SNSや口コミサイトなど、誰もが情報を発信できる時代のため、企業がダメージを受けるケースは少なくありません。
企業の信用は一度失うと回復に時間とコストがかかり、場合によっては経営そのものを揺るがす可能性さえあります。
こうした被害に対抗するためには、正確な事実確認と証拠の確保が不可欠です。
そこで本記事では、捏造の悪評・風評被害が企業に与える影響や、今後の対策法について解説します。
大切な信用と事業を守るために、ぜひ参考にしてください。
捏造の悪評・風評被害が企業に与える影響

捏造の悪評や風評被害は、企業に多大な影響を与えます。
- 信用の低下
- 事業収益の減少
- 人材確保の難化
- 離職の増加
- ブランド価値の低下
- 競争力の低下
最初は「ネットにある一部の戯言」というような内容だったとしても、それが火種となって大きな問題に発展することもあります。
具体的にどのような影響が出てくるのか、確認しておきましょう。
企業信用の低下と経済的損失

企業にとって信用は最大の資産といっても過言ではありません。
ネット上で捏造された悪評や根拠のない風評被害が広がると、これまで築いてきた信用が一気に崩れ、取引先からの契約打ち切りや新規案件の減少などにつながります。
結果として、経済的損失が発生し、会社が傾いてしまいます。
特に法人間取引では、一度信用を失うと取り戻すのは困難です。
人材確保や採用活動への悪影響

悪評・風評被害によって企業イメージが損なわれると、優秀な人材の採用にも悪影響が及びます。
求職者は企業の評判をネット上で調べる傾向が強く、悪評が目立つ企業には応募を避けるケースが増えます。
さらに、既存社員のモチベーション低下や離職率上昇といった内部への影響も深刻です。
人材の流出は組織力低下につながり、企業の競争力を弱める結果を招きます。
長期的なブランド価値の毀損

風評被害は一時的な問題に見えますが、実際には企業ブランドを長期的に毀損する危険があります。
新規顧客の獲得が難しくなり、株主や投資家からの信頼も低下することで、資金調達や事業拡大計画などにも支障をきたします。
また、ブランド価値が落ちると市場での存在感が薄れ、企業価値そのものが下がる可能性もあります。
信用とブランドを守ることは、企業の持続的成長に直結する重要な課題です。
たとえ捏造された悪評や風評被害でも、このように多大なる影響を及ぼすため、早期の対処は必須と考えましょう。
捏造の悪評・風評被害の対処は事実確認と証拠収集が重要
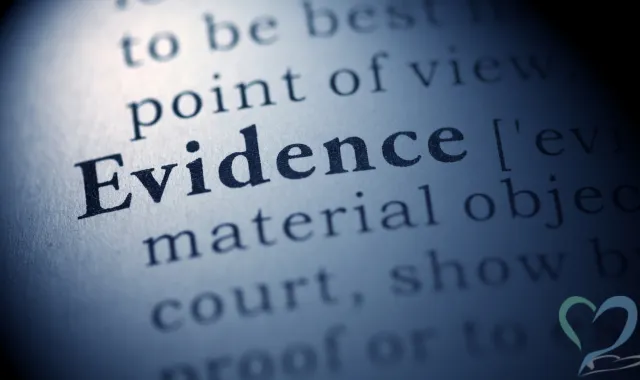
捏造の悪評や風評被害の対処として重要なのが「事実確認」と「証拠収集」です。
正しく対処をして、これらをこなせば企業への影響を抑えられます。
「事実確認」と「証拠収集」が重要な理由について解説していきます。
証拠がなければ法的対応できない
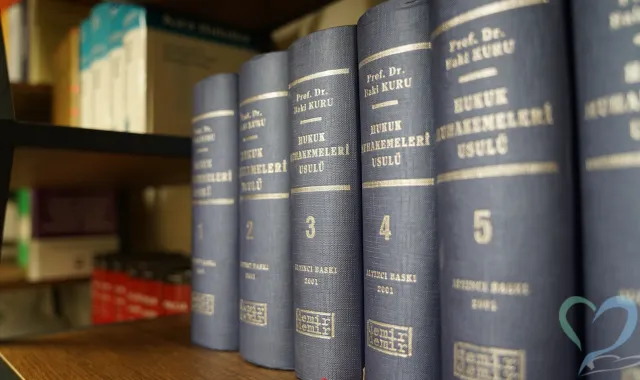
ネット上で広がる捏造された悪評に対して「被害を受けている」といった感覚的な訴えだけでは法的措置を取ることはできません。
法的に認められるためには以下の要素を満たす客観的証拠が必要です。
- 誰が
- どの媒体で
- どのように発言したのか
- どの程度拡散したのか
証拠がない状態では、企業側の主張は一方的な言い分と見なされ、投稿削除請求や損害賠償請求が却下される可能性が高くなります。
さらに、証拠が不十分なまま行動すれば、逆に企業の信用が損なわれる二次被害を招く危険性すらあります。
事実確認と証拠収集は、単に法的措置を支える材料にとどまらず、企業が自らの正当性を示し、社会的信用を取り戻すための基盤です。
証拠があるかないかで、その後の対応方針や結果が大きく変わるため、最優先で取り組むべき課題と考えましょう。
社内外への説明責任を果たす

風評被害が発生した際、企業には取引先や顧客、株主、従業員などに対して明確な説明責任が生まれます。
特に法人取引では、信頼性が低下すると契約解除や取引停止など深刻な損害が発生するため、単に「デマです」と主張するだけでは通用しません。
客観的な証拠に基づく説明ができなければ、関係者の不安を払拭できず、企業の姿勢自体が疑われかねません。
一方で、事実確認と証拠を整えたうえで社内・社外に説明を行えば、企業の透明性と誠実さを示せます。
- 投稿が事実無根である根拠
- 対応方針
- 再発防止策
説明責任を果たすことは、単なる危機管理ではなく、企業の信用基盤を守る戦略的な行動です。
証拠に基づく正確な説明なしに、信用回復は実現できないと考えましょう。
被害範囲と損害額を正確に把握できる

事実確認と証拠収集が重要な理由の一つは、被害範囲と損害額を客観的に把握できる点にもあります。
どの媒体でどの程度悪評が拡散しているのか、誰がどのような影響を受けたのかを明確にしなければ、被害の全体像は見えてきません。
また、被害の大きさを定量的に把握することで、どの事業部や取引先に優先的にフォローすべきか、どの情報管理体制を強化すべきかなどの経営判断が可能です
被害範囲と損害額の正確な把握は、感情論ではなく客観的データに基づく冷静なリスク管理を実現する鍵です。
信用回復と再発防止策の両立を目指すためにも、証拠に基づく被害評価は欠かせません。
捏造の悪評・風評被害における探偵と弁護士の役割と違い
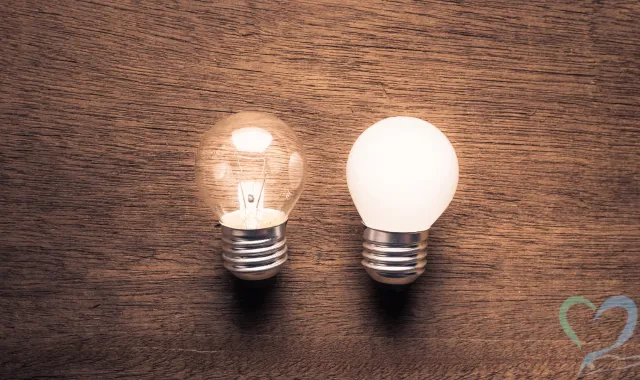
捏造の悪評・風評被害が発生したときに頼る専門家は「探偵」と「弁護士」です。
それぞれで役割が異なるため、それぞれに適切な依頼をしましょう。
ここからは捏造の悪評・風評被害における「探偵」と「弁護士」の役割と違いについて解説していきます。
探偵は証拠収集と内部調査に重要
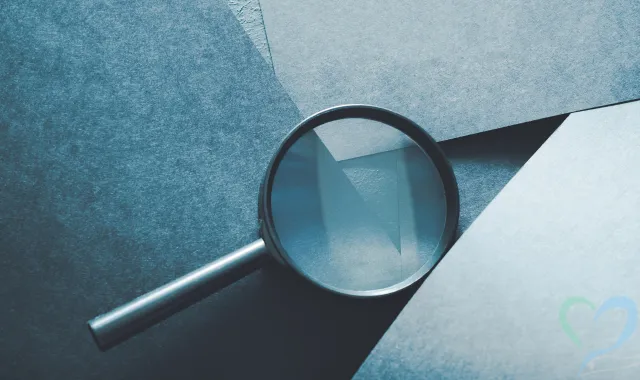
これまで説明したように、捏造された悪評や風評被害に対して法的措置を講じるためには、まず証拠の確保が欠かせません。
その役割を担うのが探偵です。
探偵はネット上の投稿特定や証拠保全に加え、内部関係者の調査や現場での行動監視まで幅広く対応できます。
これらの具体的な調査内容を順に見ていきましょう。
ネット上の投稿特定と証拠保全
風評被害の多くはネット上で急速に拡散します。
匿名掲示板やSNS、口コミサイトなどに投稿された悪評を特定し、証拠として保存することが重要です。
探偵は、ログの収集、スクリーンショットの確保、投稿日時やURLなどの詳細情報を専門的に整理します。
これにより、後の削除請求や発信者情報開示請求に必要な証拠資料が揃います。
内部関係者や漏洩源の調査
ネット上の風評被害の原因が、内部からの情報漏洩によるケースも少なくありません。
社員や関係者が意図的に情報を外部に流したり、退職者が不満から内部情報を投稿する事例もあります。
探偵は、社内ヒアリングや関係者の行動確認などを活用して漏洩源を特定します。
誰が情報を持ち出したのかを突き止めることで、再発防止策の立案や、社内処分の判断材料として活用可能です。
現場調査・行動監視による裏付け
風評被害の発信源が特定の人物や団体と推定される場合、現場調査や行動監視によって事実関係を裏付けられます。
探偵は、対象者の行動パターンや面会相手を調査し、誰と接触しているか、どこに出入りしているかを詳細に記録します。
たとえば、競合企業の担当者と頻繁に会っている、取引先に虚偽情報を流している、といった具体的な行動を把握可能です。
これにより、ネット上の証拠だけでは補えない物理的証拠を追加でき、法的措置の強力な裏付けとなります。
調査報告書の作成
探偵が行う調査の最終的な成果物は、調査報告書という形でまとめられます。
この報告書には、証拠写真や動画、行動記録、面会相手の情報などが詳細に整理され、客観的な証拠資料として活用できます。
調査報告書は、弁護士による法的措置を進める際の根拠資料として不可欠です。
裁判や削除請求、損害賠償請求の場面でも、正確かつ詳細な報告書があることで主張の信頼性が大きく高まります。
また、社内外への説明資料として活用することで、透明性を示し関係者の理解と信頼を得る役割も果たします。
調査報告書は単なる報告書類ではなく、信用回復と再発防止を実現するための重要な武器です。
弁護士は法的措置と交渉に重要

探偵による証拠収集が整った後、実際に法的対応を行うためには弁護士の存在が欠かせません。
弁護士は、集めた証拠をもとに投稿者の特定、投稿削除請求、損害賠償請求といった具体的な法的措置を進めます。
証拠と法的知識を組み合わせることで、強制力のある対応が可能になり、被害の拡大防止と信用回復に直結します。
ここからは、弁護士が実際に担う具体的な手続きを見ていきましょう。
発信者情報開示請求の実施
匿名で投稿された誹謗中傷や虚偽情報の発信者を特定するためには、発信者情報開示請求が必要です。
弁護士は、証拠を基にプロバイダやプラットフォーム運営会社に対して開示請求を行い、投稿者の氏名や住所、接続情報などを特定します。
この手続きは法的な知識と手順が複雑で、個人や企業が独自に行うことは現実的ではありません。
発信者情報の特定ができれば、投稿削除や損害賠償請求など、さらに踏み込んだ法的対応に進めます。
開示請求は、風評被害対策において初期段階の重要なステップです。
投稿削除請求や損害賠償請求
発信者が特定できた後は、被害を直接的に止めるために投稿削除請求を行います。
弁護士は証拠資料を基に、プラットフォーム運営会社や投稿者に対して法的根拠を示し、問題となる投稿の削除を求めます。
これにより拡散を防ぎ、企業の信用回復を加速させることが可能です。
加えて、投稿によって生じた損害額を明確にし、損害賠償請求を行うことで、被害の補填を図ります。
損害賠償請求は金銭的な補償にとどまらず、再発防止や相手側への抑止効果という点でも大きな意義があります。
これらの法的手続きを確実に進めるためには、専門知識を持つ弁護士の関与が不可欠です。
取引先やメディアへの法的説明
風評被害が発生した際、取引先や関係企業、メディアに対して正確な情報を共有することも弁護士の重要な役割です。
証拠と法的根拠を示した説明を行うことで、メディアを通して企業が被害者であることを明確にし、無用な誤解や二次被害の拡大を防ぎます。
特に取引先に対しては、信頼関係を維持するために迅速かつ慎重な対応が求められます。
また、メディアへの説明は情報が一方的に拡散されるのを防ぎ、事実を正しく報道してもらうための重要な機会です。
弁護士の介入によって、感情的な説明ではなく、法的に整理された理論的説明が可能になり、信頼性の高い対応が実現します。
訴訟や交渉全般の代理
風評被害の解決を法的に進める際、最終的には訴訟提起や交渉が必要になるケースがあります。
弁護士は、集めた証拠を基に損害賠償請求訴訟を起こすほか、相手方との示談交渉や和解条件の調整も代行します。
交渉は感情的対立を避け、客観的かつ戦略的に進める必要があり、単独対応は困難です。
弁護士が代理人として関与することで、訴訟や交渉の負担を軽減し、企業のリスクを最小化できます。
また、第三者に対しても法的な強制力を示せるため、問題解決のスピードと確実性が大きく向上します。
法的措置を最終手段とする際には、弁護士の存在は不可欠といえるでしょう。
悪評・風評被害が広まっているときに企業が今すぐ始めるべき初動対応

風評被害が広まった際、感情的に反応するのではなく、冷静に初動対応を進めることが被害拡大を防ぐ最大の鍵です。
初期対応の遅れは、被害範囲の拡大や関係者との信頼関係崩壊につながります。
そこで、ここからは企業がすぐに取り組むべき具体的な行動を紹介します。
悪評データの保存と整理

風評被害に対する初動対応として最優先すべきは、悪評に関する全データの保存と整理です。
被害状況を正確に把握するには「いつ」「どこで」「どのような投稿があったのか」を詳細に記録する必要があります。
具体的に保存・整理したい内容は以下のとおりです。
- 該当ページのスクリーンショット
- URL
- 投稿日時
- 拡散状況
これらの情報は、後に法的措置や説明資料の根拠となる重要な証拠です。
万が一データが欠落すると、発信者情報開示請求や損害賠償請求の際に正当性を示せなくなる恐れがあります。
データの保存と整理をし、いち早く信頼回復の基盤を作りましょう。
社内体制の見直しと情報統制

風評被害が発生したとき、企業内の情報共有と体制が混乱すると、事態がさらに深刻化します。
まず、社内で情報共有ルールを明確にし、被害状況や対応方針を全社員に一貫して伝えることが重要です。
特に、外部からの問い合わせ窓口や公式コメントの統一を徹底しなければ、不要な誤解や二次的な誤情報が拡散する恐れがあります。
また、経営陣、広報、法務部門などの関係部署が協力して迅速に意思決定できる体制を整えることも欠かせません。
社内体制の見直しと情報統制をし、より企業が前向きに進めるよう努めましょう。
外部専門家への早期相談

風評被害が拡大してしまうと、自社内だけの対応では限界があります。
専門的な知識や経験がなければ、証拠保全の漏れや対応の遅れが生じ、事態がさらに悪化する恐れがあります。
早期に探偵や弁護士などの外部専門家へ相談することで、被害拡大を防ぎ、信用回復への動きを一歩早めることが可能です。
被害が深刻化する前に、迷わず専門家に相談し、迅速な対応を始めましょう。
捏造の悪評・風評被害に関するよくある質問


捏造された悪評でも削除できますか?

可能です。投稿内容が事実無根であることを証拠で示せれば、プラットフォームや投稿者に対して削除請求を行えます。

風評被害の証拠がなくても損害賠償請求できますか?

できません。被害の発生や拡散状況を裏付ける証拠がなければ、損害額や責任の立証ができず、請求が認められません。

調査費用はどれくらいかかりますか?

被害内容や調査範囲によって変わりますが、探偵の調査費用はおおよそ30万円〜100万円程度、弁護士費用は数十万円〜場合によっては100万円以上かかることもあります。具体的な金額はケースごとに大きく異なるため、事前に相談して見積もりを確認することが大切です。

探偵と弁護士のどちらに先に相談すべきですか?

まずは探偵への相談が有効です。証拠がなければ弁護士も法的措置を進められないため、先に証拠収集と状況把握を行うことが重要です。

社内で情報が漏れている可能性も調査できますか?

調査可能です。探偵は内部関係者の行動やデータ流出の経路を調査し、漏洩源を特定できます。
捏造の悪評・風評被害の対処にはファミリー調査事務所にお任せください

捏造された悪評や風評被害は、企業の信用と事業継続に深刻な影響を及ぼします。
放置すれば被害は拡大し、取引先や顧客、社員の信頼を失うリスクが高まります。
そのため、迅速に探偵や弁護士に依頼して証拠収集・法的措置を行い、信頼回復に努めることが重要です。
ファミリー調査事務所では、投稿者特定や内部調査などの証拠収集を行っており、さらに悪評・風評被害問題に精通している提携弁護士の紹介も可能です。
豊富な実績と専門知識を活かし、迅速かつ確実な対応で企業の信用回復をサポートします。
被害が深刻化する前に、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
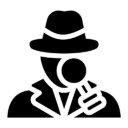
執筆者:米良
長年の情報収集経験を有し、英語での情報分析も得意とする。豊富な海外調査実績をもとに、国内外の問題を独自の視点で解説します。