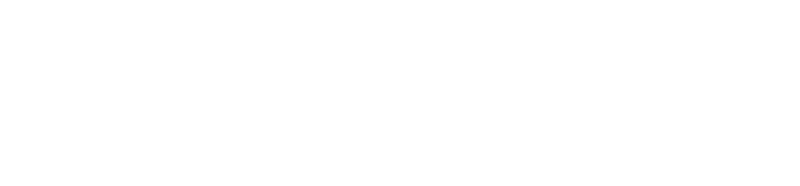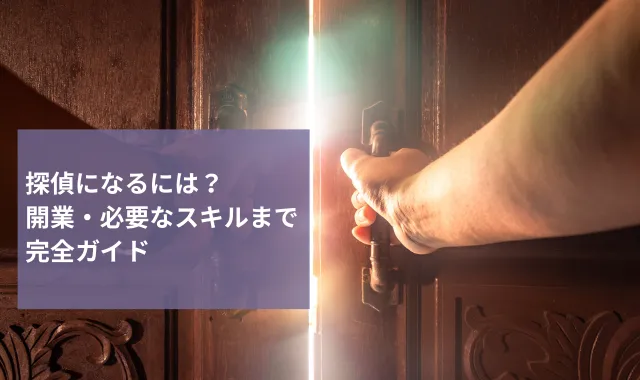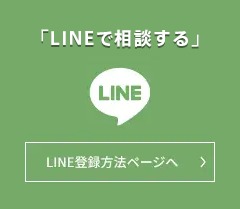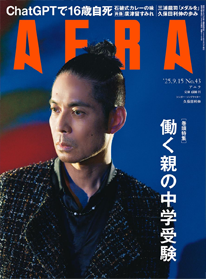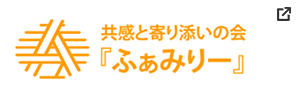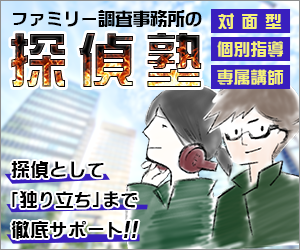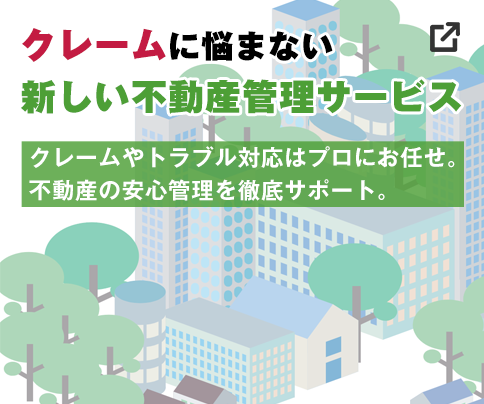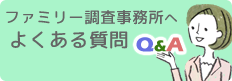「個人で開業はできる?」
探偵になるには、探偵事務所に就職したり、個人で開業したりと、さまざまな方法があります。
特別な国家資格は不要なので、端的にいえば誰でもなれますが、持っておきたい資格やスキルはいくつかあります。
また、探偵になる前に、給料や将来性、理想と現実のギャップなどを理解しておくことも大事です。
そこで本記事では、探偵になりたい人に向けて覚えておきたいこと、探偵になる方法などを解説していきます。
目次
探偵になるにはどんな方法がある?主な3つのルートを解説

探偵になるには、主に以下の3つの方法があります。
より自分に合った方法を見つけて探偵になりましょう。
探偵事務所に就職して経験を積む

- 現場で調査技術と運用フローの全体像を学べる
- 給与を得ながら経験を積めるため経済的リスクが少ない
- 実際の依頼対応を通じて、対人スキルや調査判断力も鍛えられる
- 調査対象や勤務時間は選べず、柔軟な働き方は難しい
- 雑用・下積み業務が長く続くことがある
- 自分に合った探偵事務所を見つける必要がある
探偵事務所に就職すれば、日常的に尾行・張り込み・撮影を行うことで、実践的な調査スキルが身につきます。
給与を得ながら学べるため、学校や独立とは異なり生活面での負担を小さく抑えられるのも大きなメリットです。
一方で、業務内容やシフトは事務所の判断に従うため、自由度は高くありません。
また、精神的・体力的に負荷の高い案件に配属されたり、報告書作成や機材管理といった裏方の作業を任せられることもあります。
とはいえ、負荷の高い案件や裏方の作業も、今後探偵として生きていく以上、避けられない業務といえます。
自由度は高くないとはいえ、働きながら総合的に学べるため、長期的にいえば独立やキャリアアップの基礎となるでしょう。
探偵学校・養成所でスキルを学ぶ

- 基礎から体系的に調査技術と法知識を学べる
- 自主的な練習や反復がしやすく、自分のペースで進められる
- 就職支援・独立支援付きのスクールもある
- 学費や教材費などのコストが発生する
- 卒業しても即戦力と見なされるとは限らない
- 学習だけでは実際の現場対応力は身につきにくい
探偵学校や養成講座では、尾行・張り込み・撮影・報告書の作成といった技術を習得できます。
座学では探偵業法や個人情報保護法なども扱われ、実務に関わる法律を基礎から学べるのもメリットです。
ただし、学費が必要であることや、実務経験がない状態では就職先の選択肢が限られることもあります。
また、現場では想定通りに進まないケースも多く、座学だけでは対応力が不足する場合もあります。
結果として、学校で培った知識が、あまり役に立たず、「就職して給料をもらいながら経験を積んだほうが良かった」と感じることも少なくありません。
学校や養成所ならではの、講座修了後の進路やサポート体制も確認した上で、自分に合った学校を選びましょう。
個人で開業する(フランチャイズ)

- 自分の裁量で営業や案件対応ができる
- 調査費用や報酬を自分で設定できる
- フランチャイズを利用すれば開業支援を受けられる
- 開業前に届出・設備・書類などの準備が必要
- 集客・営業・契約などもすべて自分で行う
- 経営が安定するまで時間がかかることが多い
個人での開業は、働き方や料金体系を自由に決められるため、自分の裁量で事業を進めたい人に適しています。
ただし、経験や実績が不足していると、経営が安定するまでに時間がかかる傾向があるため、開業は慎重に行なうべきです。
また、個人で探偵業を始めるには、まず営業所や機材の準備に加えて、集客・営業・契約なども自分で行う必要があります。
そうした課題に対して有効なのが、フランチャイズ制度を利用する方法です。
業務マニュアルや営業支援を受けながら開業できるため、未経験者でもスタートしやすいです。
集客・契約などもフランチャイズであれば支援してもらえるため、実質的に個人で開業するデメリットの多くを避けられます。
なお、ファミリー調査事務所では、個人での独立を支援するフランチャイズ制度を提供しています。
未経験でも始められるので、興味のある方は一度「公式フランチャイズ募集ページ」をご確認ください。
探偵を開業する際の手続きを解説

探偵を開業する際の大まかな流れは以下の通りです。
それぞれの流れをチェックして、これからの開業をよりイメージしてみましょう。
1. 営業所の確保や設備・機材・名刺の準備

探偵として開業するには、来客対応可能な営業所を確保し、机・椅子・パソコン・通信環境などの業務設備を整えます。
調査に必要なカメラや録音機器、通信端末、バッテリー、車両備品なども事前に揃える必要があります。
営業ツールとしては、名刺・封筒・パンフレット類、事務印・表札・電話番号なども開業前に準備しておきましょう。
なお、これらはすべて個別に選定・購入・設置が必要なため、初期段階での負担が大きくなりがちです。
負担を減らしたい場合は、フランチャイズに加盟し、機材リストや帳票類の雛形、営業所仕様などの情報提供を受けるのも一つの手です。
2. 必要書類の準備

探偵業を開業するには、営業開始日の前日までに所轄の公安委員会に「探偵業開始届出書」を提出する必要があります。
届出には、以下の添付書類が求められます。
- 履歴書
- 住民票
- 誓約書
- 身分証明書
書類ごとに取得先や必要書式が異なるため、事前に所轄の警察署で最新の様式を確認しておきましょう。
証明書類には発行からの有効期限が設けられているため、収集時期にも注意が必要です。
3. 探偵業届出書を提出する

必要書類が揃ったら、営業所を管轄する警察署の防犯係に届出を行います。
受付時間や窓口対応は警察署ごとに異なるため、事前に電話などで確認してから訪問するのが確実です。
届出時には、書類の記載内容に不備がないかをその場でチェックされるため、署名や押印漏れがないよう注意しましょう。
添付書類の有効期限が切れていると再提出になることがあるため、直前に再確認することも重要です。
書類一式の受理後は、所轄の案内に従って手続きを進めます。
4. 標識を掲示して開業する

探偵業の届出が完了したら、内閣府令の様式に従った「標識」を自ら作成し、営業所の見やすい場所とウェブサイト上に掲示する義務があります。
掲示を整えたうえで、正式に探偵業としての営業を開始できます。
標識の様式や記載事項は変更されることがあるため、所轄警察署で最新の運用を確認しておきましょう。
5. 開業後に守るべき法的義務を理解する

探偵業を始めた後は、法令に基づいた業務運用を継続的に行わなければなりません。
たとえば、契約時には「重要事項説明書」と「契約書」の交付・保管が義務付けられ、内容は法定基準に従う必要があります。
調査報告の方法や、依頼者の個人情報を第三者に漏らさない義務もあり、違反すれば行政処分や業務停止の対象になります。
このように、開業後も多くの法的義務に対応し続ける必要があり、実務上の負担は少なくありません。
フランチャイズであれば、法令に関する知識を開業前に学べるため、不安な場合はぜひ活用したいところです。
探偵になるために理解しておきたいスキル・資格

探偵は未経験でも始められるケースが多いですが、実際に活躍する探偵・有能とされる探偵には共通したスキルや資格があります。
より探偵として活躍するためにも、ご自身に該当するものがないか一度チェックしておきましょう。
尾行や張り込みを行うための観察力と持久力

探偵業務では、対象者の行動を長時間にわたって追跡・監視する必要があり、集中力と観察力が求められます。
たとえば尾行中には、対象者のわずかな行動の変化から目的地や意図を読み取る判断力が必要です。
また、数時間以上に及ぶ張り込みを想定して、体力と忍耐力を維持できる持久力も不可欠です。
狭い場所や車内など、一定の姿勢で待機する場面も多く、予想以上に身体への負担が大きくなります。
体力面に自信がない場合は、事前に軽い運動習慣を取り入れておくと役に立つでしょう。
状況を的確に判断する冷静さと柔軟な対応力

調査現場では、対象者が予期せぬ行動をとる場面や、計画通りに進まない状況が頻繁に発生します。
その際に慌てず状況を整理し、適切な判断を下すためには、冷静さと的確な判断力が欠かせません。
たとえば、対象者が突然タクシーに乗って移動したり、進行先が立ち入り禁止区域だったりするケースでは、即座に代替手段を考える必要があります。
また、交通規制や周囲の状況に応じて、待機場所や尾行ルートを柔軟に切り替える対応力も求められます。
想定外の状況でも判断を誤らず、依頼者の期待に応える調査を続けるためには、こうした力が実務上で非常に重要です。
証拠を正確に記録するための撮影スキルと記録能力

調査では、浮気や素行の証拠を画像や映像で残すことが重要であり、ブレのない撮影や構図の判断が求められます。
対象者の顔や同行者、入店先の看板などが明確に写るよう撮影するには、カメラの設定や距離感の調整に関する知識と経験が不可欠です。
加えて、撮影したデータを時系列で整理・保管し、報告書として依頼者に提出するまでの記録スキルも重要です。
証拠としての信頼性を保つには、写真に撮影日時や撮影場所の情報(タイムスタンプや位置情報)を正確に残すことも求められます。
撮影技術の基礎を体系的に学びたい場合は、フォトマスター検定などの民間資格を通じて知識を深めておくのも有効です。
調査時に不審にならないコミュニケーション力

探偵は、現場で目立たず自然にふるまうことが求められ、不審な行動を取らないための立ち居振る舞いが重要です。
張り込み中に近隣住民から声をかけられた際や、尾行中に職務質問を受けた場合には、冷静に受け答えしつつその場の空気になじむ対応力が必要になります。
それに加えて、依頼者から信頼を得るための説明力や、調査目的を正確に把握するための対話力も求められます。
また、複数人での調査を行う際には、状況を共有しながら連携するためのコミュニケーション力が欠かせません。
現場での対応力を高めるために、コミュニケーション能力認定やメンタルケア心理士などの民間資格を通じて対人スキルを学んでおくのも一つの手です。
的確に追跡するための運転スキル・土地勘

車両を使って対象者を追跡する場合には、高い運転スキルと状況判断力が必要です。
前方車両との距離を保ちつつ、信号や交通状況に応じて自然に追跡を続けるには、経験に裏打ちされた技術が求められます。
また、地元の道路構造や渋滞ポイント、抜け道などに関する土地勘があることで、対象者を見失うリスクを減らせます。
調査では車両を使う場面が多いため、自動車運転免許は探偵として働く上でほぼ必須の資格であることは理解しておきましょう。
探偵に向いている人

- 小さな変化に気づける観察力がある人
- 長時間の待機や移動にも耐えられる人
- 状況に応じて冷静に行動できる人
- 信頼関係を築くのが得意な人
- 協調性を持って動ける人
探偵業務では、張り込みや尾行といった緊張感のある現場対応が続くため、集中力と忍耐力が欠かせません。
依頼者と良好な関係を築ける対話力や、チーム内でスムーズに連携する協調性も、実務の中で重要な役割を果たします。
探偵に向いていない人

- 長時間じっとしていることが苦手な人
- 緊張する場面で焦りやすい人
- 人の行動を観察することに興味がない人
- 秘密を守るのが苦手な人
- 一人で黙々と作業するのが極端に苦手な人
探偵の仕事は地道な作業や待機時間が多く、集中力が続かない人には負担が大きく感じられることがあります。
また、調査内容は依頼者にとって極めてプライベートな情報であるため、秘密を守る意識が欠けていると信頼を損なうリスクがあります。
性格や行動特性によっては、ほかの職種のほうが力を発揮できる場合もあるため、事前に仕事内容との相性をしっかり確認することが大切です。
探偵の働き方や収入の実態
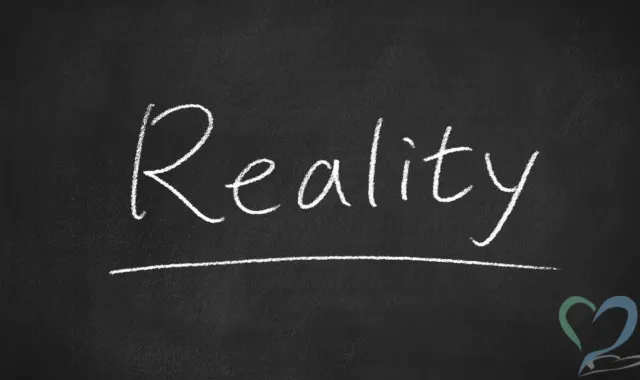
探偵として働く場合に気になってくるのは、働き方(雇用形態)や収入などかと思います。
ここからは、そんな探偵のリアルな実態について解説していきます。
雇用形態

探偵として働く場合、雇用形態は主に正社員・アルバイト・自営業の3つに分かれます。
正社員は調査会社に所属し、安定した給与と研修制度を受けながら本格的な調査業務に携わることができます。
アルバイトは、主に張り込みや簡易調査などの補助業務を担う立場で、未経験からスタートしやすく、働き方の柔軟性があるのがメリットです。
また、自ら探偵業の届出を行い、営業から調査まで一貫して担う自営業(個人事業主)としての働き方もあります。
自分で業務管理ができるため、独立志向の人には適した形態です。
どれが正解というものはないので、ご自身に合った働き方を見つけましょう。
収入

| 働き方 | 収入の目安 |
|---|---|
| 正社員 | 月給20万〜35万円程度(+歩合) |
| アルバイト | 時給1,100〜1,800円程度 |
| 自営業(個人事業主) | 月0〜50万円以上も可 |
探偵の収入は雇用形態や働き方によって大きく異なります。
正社員の場合は、月給20万〜35万円程度が一般的で、調査件数や成約率に応じて歩合給が加算されるのが一般的です。
アルバイトの場合は、時給1,100〜1,800円程度が相場で、張り込みや尾行などの実働時間に応じて支給されます。
自営業として活動する場合は、受注件数や契約単価により大きく変動し、月によっては0円から50万円以上となることもあります。
成果報酬の割合が大きい職場もあるため、安定収入を希望する場合は給与体系を事前に確認しておきましょう。
キャリアパス
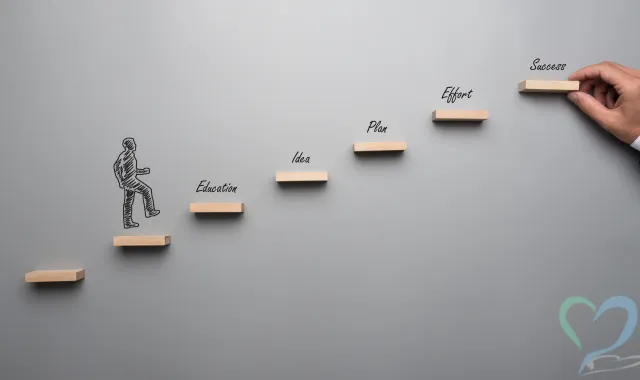
探偵としてのキャリアは、未経験から補助業務を担い、段階的に調査の中核を担う立場へと進んでいきます。
大まかなステップとしては以下の通りです。
- 1.補助スタッフからスタート
- 2.調査員として独り立ち
- 3.主任や班長としてチームをまとめる立場へ
- 4.マネジメント職に昇進
- 5.社長として経営を担う
はじめは張り込みや記録補助などの実務を通じて、尾行や撮影、報告書作成のスキルを身につけていきます。
その後、案件を単独で任される調査員となり、実務経験を積むことで主任やリーダーなどの役職に進むことも可能です。
マネジメント職では、調査班の統括や依頼者対応、後進の育成といった業務を担うことになります。
自分の目指す将来像に合わせて、必要なスキルと経験を段階的に積み重ねていきましょう。
勤務時間・休日

探偵の勤務時間は、対象者の行動に合わせる必要があるため不規則で、一般的な会社員とは異なります。
1回の調査につき8〜10時間前後の拘束が発生することも多く、特に浮気調査では18時〜翌1時、21時〜翌5時などの夜間帯が中心になります。
また、対象者が動きやすい土日や祝日に調査が集中するため、週末勤務や連休中の出勤も発生しやすい業界です。
休日はシフト制が多く、月6〜8日程度が目安となります。
完全週休2日制を採用している事務所は一部で、調査がない日を休日として調整するスタイルが一般的です。
こうした働き方に無理なく対応するためにも、スケジュール管理や体調管理が求められます。
将来性

探偵業界は浮気調査や素行調査を中心に、一定の需要が継続している分野です。
高齢者の見守り調査や企業向け調査など、ニーズの多様化も進んでおり、活躍の場は広がりつつあります。
インターネットやSNSの普及で、個人の行動が見えにくくなっていることもあり「第三者による客観的な調査」の重要性は増す一方です。
また、近年はAIや自動化の進展が進んでいますが、探偵業務の多くは現場での判断・観察・対人対応など、人間の判断力に強く依存しています。
そのため、AIに奪われにくい仕事とも言えます。
実際、全国的に探偵事務所の求人は継続しており、未経験者の採用や社内育成を行う事務所も少なくありません。
専門性と誠実な対応力を磨くことで、長期的に活躍できる仕事としての将来性は十分あるといえるでしょう。
探偵になりたい人が覚えておくべき注意点

探偵という仕事は知名度はあるものの、実態はあまり知られておらず、思わぬ勘違いをしてしまうことも少なくありません。
以下の探偵になる前に覚えておきたい注意点をまとめたので、参考にしてください。
理想と現実のギャップを知ること

探偵は映画やドラマのような派手な活動を連想されがちですが、実際の業務は地道な作業の積み重ねです。
張り込みでは数時間動かずに待機し、尾行中も目立たず自然に行動する必要があります。
天候や環境に関わらず調査を続けることも多く、体力と集中力の維持が求められます。
また、自由に動き回る仕事ではなく、調査計画や依頼内容に沿って慎重に行動する必要があります。
想像とのギャップを感じることで離職に至るケースもあるため、現実を理解したうえでの覚悟が重要です。
推理小説や漫画・アニメによくある「推理をする探偵」「警察の捜査に介入する探偵」も実際には存在しないので留意しておきましょう。
法令遵守と依頼者対応の責任が大きい

探偵の調査は、法律の枠内で行うことが絶対条件です。
尾行や撮影の方法を誤れば、プライバシー侵害や違法行為とみなされる可能性があります。
また、依頼者からは調査結果に対して高い正確性と誠実な対応が求められます。
事実に基づいた報告書を作成し、感情的にならずに説明を行う姿勢も重要です。
特に探偵への依頼で多い「不倫調査」は依頼者にとって人生を大きく左右する内容でもあるため、強い責任感を持つ必要があります。
悪徳な探偵事務所もある

探偵業界には法令を守り誠実に運営されている事務所がある一方で、対応や契約に不備のある事務所も存在します。
たとえば、料金体系が不明確だったり、調査内容の説明が不十分なまま契約を進めるケースには注意が必要です。
違法調査を黙認するような体制の事務所では、働く側もリスクを背負うことになります。
求人に応募する際は、事前に実績や社内の体制、届出番号の有無などを確認することが大切です。
信頼できる事務所で働き、長く安心して経験を積みましょう。
よくある質問|探偵になるには?


探偵に学歴や資格は必要?

学歴や資格は不要で、現場での判断力や責任感が重視されます。未経験者向けの研修制度がある事務所も多いため、まずは情報を集めてみましょう。

年齢で不利になることはある?

年齢よりも適性が重視され、社会経験が強みになることもあります。どちらにしても事務所によって異なるので、まずは採用方針を確認しましょう。

女性でも探偵になれる?

女性でも活躍できる仕事で、性別による制限はありません。女性による相談対応が必要なケースも多いため、男性より求められていることも珍しくありません。

副業でも探偵はできる?

勤務時間の都合から副業との両立は難しい場合があります。まずは短時間の勤務やアルバイト枠から検討してみてください。

読んでおいたほうが良い本はある?

実務書や法知識に関する本を読むことで理解が深まります。一般的な探偵の入門書を読んでおきましょう。
ファミリー調査事務所で探偵として開業をしませんか?

探偵として独立を目指す方にとって、最初の一歩は不安も多いかもしれません。
ファミリー調査事務所では、未経験からでも開業できるよう支援体制を整えています。
実績ある調査ノウハウや業務フォローを受けながら、自分の地域で調査業務を行えるよう一緒に開業プランを構築していきます。
まずはフランチャイズ制度の詳細をご覧いただき、自分に合った働き方を検討してみてください。
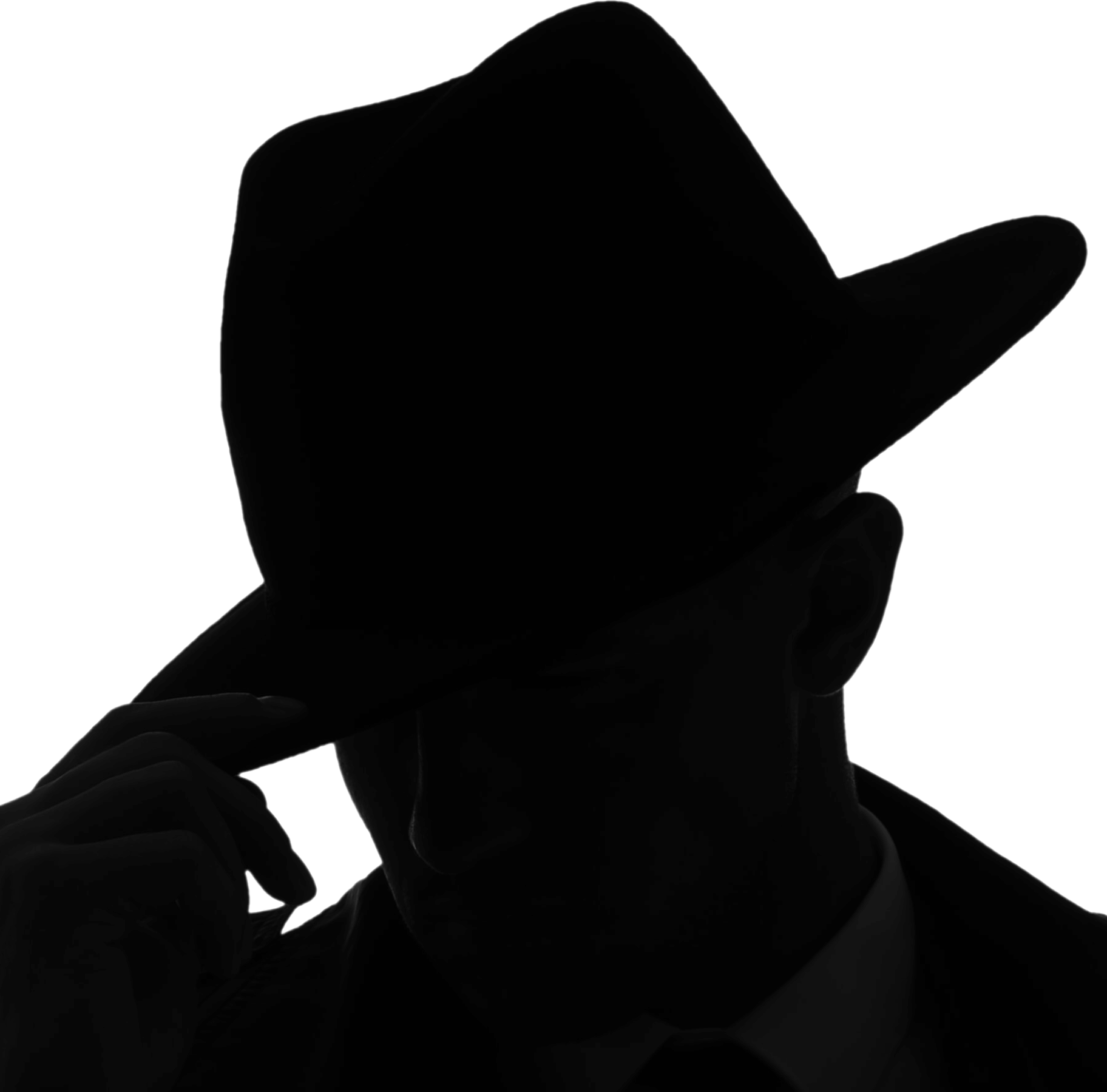
執筆者:Kazuya Yamauchi
探偵調査歴20年。国内外の潜入調査、信用に関する問題、迷惑行為、企業や個人生活での男女間のトラブルなど、多岐にわたる問題を解決してきました。豊富な経験と実績を基に、ウェブサイトの内容監修や執筆も行っています。