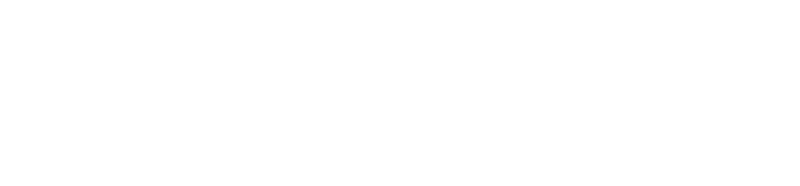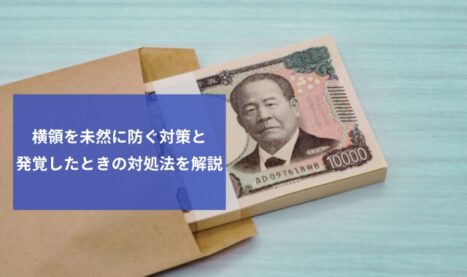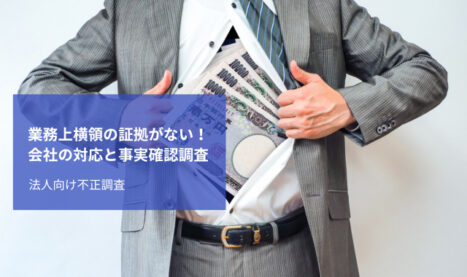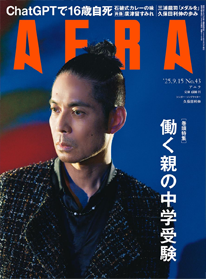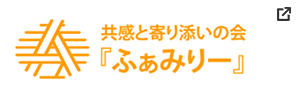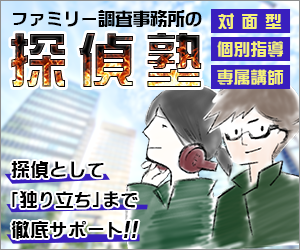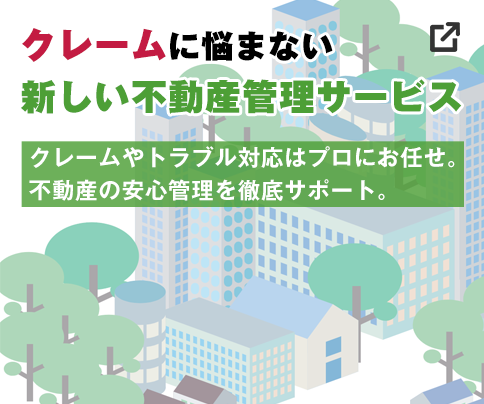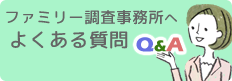「横領が発覚したけど、該当の従業員は退職後でどうすればいいか分からない」
「退職後に横領が発覚してからでは遅い?」
企業での横領は、小さいものも含めると意外にもさまざまなところで発生しています。
とはいえ、実際に横領が発覚するとどのように対処するべきなのかわからない人がほとんどでしょう。
従業員の退職後に発覚するケースではなおさらです。
そこで本記事では、従業員が退職後に横領が発覚した場合の対処法、証拠の集め方について解説します。
横領は正しく対処しなければ、さらなるトラブルが発生することも少なくありません。
ぜひ本記事を参考にしていただき、スムーズな解決を目指しましょう。
従業員の退職後に横領が発覚したときの対処法

さっそく従業員の退職後に横領が発覚したときの対処法を、5つのステップで解説していきます。
- まずは証拠を集める
- 証拠の保全を行う
- 本人に連絡し事実確認をする
- 損害賠償請求・刑事告訴をする
- 再発防止・社内体制の見直しをする
それぞれの流れを確認し、スムーズな解決を目指しましょう。
1.まずは証拠を集める

まずは証拠を集めてください。
横領で証拠になるものを以下にまとめたので、こちらを参考に証拠を集めましょう。
| 主な証拠 | 具体的な内容 |
| 客観的証拠 | 防犯カメラの映像・レジの記録など |
| 物的証拠 | 横領品の所持・急な高額消費など |
| 証言・供述 | 本人の自白やメモ・第三者の証言 |
| 状況証拠 | 金銭が消えた直後に帰宅した・所持品のチェックを拒否したなど |
なお、状況証拠はあくまで補助的な役割を持ちます。
そのため、状況証拠だけで犯人と思わしき人を問い詰めてしまうと、今後大きな問題に発展する可能性も否めません。
今後の損害賠償請求・刑事告訴を視野にいれて、慎重に証拠を集めましょう。
2.証拠の保全を行う

証拠が集まったら証拠の保全をしてください。
ほとんどの人は横領の対応に慣れていないため、このような基本ではあるものの重要なことを疎かにしがちです。
デジタルデータの証拠ならバックアップをとる、アナログなら金庫に保管するなど、今後証拠の紛失をしないよう厳重にしましょう。
3.本人に連絡し事実確認をする

証拠がある程度揃ったら本人に連絡して事実確認をしましょう。
本人の言い分を聞いて意図や経緯を明らかにしてください。
本人の自白を引き出せば何よりの証拠となりますし、今後の対応についても考えやすくなります。
ただし、問い詰めるという形ではなく、冷静に事実確認の場を設けることを第一に考えましょう。
なお、公平性や記録性を担保できるので、可能であれば弁護士や第三者を立ち会わせることをおすすめします。
4.損害賠償請求・刑事告訴をする
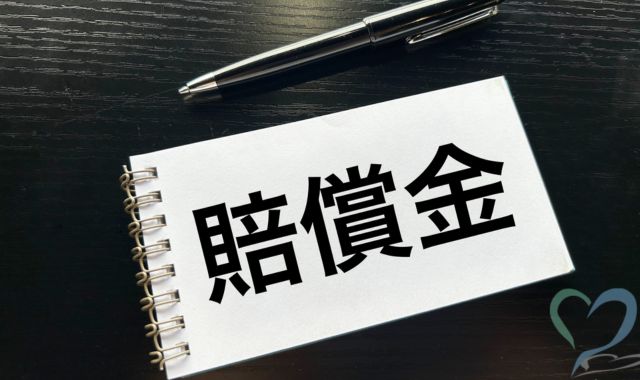
事実確認後は、その後の対応を考えましょう。
一般的には損害賠償請求や刑事告訴をします。
| 損害賠償請求(民事) | 刑事告訴(刑事) | |
| 目的 | 損害をお金で取り戻す | 犯罪として処罰してもらう |
| 手続き先 | 裁判所 | 警察・検察 |
| 請求する相手 | 加害者本人 | 国(加害者への処罰を求める) |
| メリット | 被害回復が期待できる | 社会的制裁・再発防止になる |
| デメリット | 相手に支払能力がないと回収困難 | お金は戻らない |
損害賠償請求はいわゆる民事で、端的にいえば金銭的な損失を回復するために行います。
刑事告訴はいわゆる刑事で、加害者に対して処罰をしてほしい場合に行います。
お金を取り戻したい場合は損害賠償請求を、犯罪という形にして社会的な制裁をしたい場合は刑事告訴をしましょう。
5.再発防止・社内体制の見直しをする

損害賠償請求・刑事告訴で、横領に対する対処は一区切りとなりますが、今後のためにも再発防止・社内体制の見直しをすることをおすすめします。
一度横領が起こったということは、社内体制に何らかの欠陥があったということでもあります。
そのため、社内体制が改善されないと根本的な解決とは言えません。
「なぜ退職後になるまで発覚に気づけなかったのか」「発覚が遅れた理由は」「横領しやすい環境であったか」などを社内で分析してみてください。
従業員退職後の横領に関して覚えておきたいポイント

従業員が退職したあとに横領が発覚するケースでは、企業側が適切な対応を取るために、事前の備えが何より重要です。
退職後は証拠の確保が難しくなり、連絡が取れなくなることで法的手続きすら行えない可能性もあります。
ここからはこのような、従業員退職後に発覚した横領に関して、覚えておきたい以下3つのポイントを解説します。
- 証拠がなければ責任追及は困難
- 退職後は特に証拠が残りにくくなるリスクが高い
- 連絡先が分からず損害賠償請求が難航することも
横領について正しく理解し、今後スムーズな対応をとれるようにしましょう。
証拠がなければ責任追及は困難

横領に対して法的措置をとるには「誰が・何を・どう行ったのか」を示す証拠が必要です。
たとえば「レジ金が消えた」「勤務中はその従業員だけだった」という状況だけでは、直接的な証明にはなりません。
防犯カメラや会計記録、内部監査の記録など、客観的な裏付けが不可欠です。
不審な金銭の動きがあった場合は、迷わず記録を保存し証拠として残す習慣をつけましょう。
なお、現状で証拠がない場合は、探偵に調査を依頼するといった行動を早めに検討してください。
退職後は特に証拠が残りにくくなるリスクが高い

退職して時間が経つほど、証拠は失われやすくなります。
監視カメラの映像記録が自動消去されたり、関係者の記憶が曖昧になったりと、後追いの調査では限界が出やすいのが現実です。
たとえば、防犯カメラが2週間で上書きされる設定だった場合、発覚が遅れると肝心な証拠がもう残っていないことも。
「少しでも怪しい」と感じたら、退職前に確認・保存しておくことが何よりも大切ですが、すでに退職しているなら、今すぐにでも証拠の保全・調査を進めましょう。
連絡先が分からず損害賠償請求が難航することも
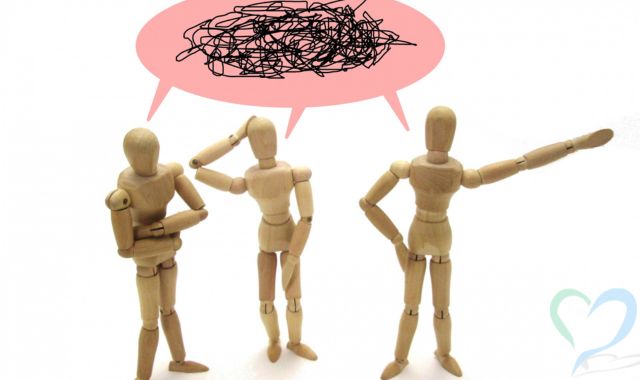
たとえ不正を立証できても、相手に連絡がつかないと法的な請求手続きが進められません。
たとえば、住所変更や連絡手段の遮断により、訴訟に必要な「特定送達(書類送付)」ができないと、損害賠償を事実上断念せざるを得ません。
このような状況を回避するためにも、相手の現住所や所在を正確に把握することが重要です。
もし連絡が取れない・居場所が不明という場合には、調査の専門家である探偵に依頼して、住所や勤務先などを特定してもらうという選択肢があります。
法的手続きを進めるためにも、証拠を集めるだけでなく住所の特定も並行して進めましょう。
退職後に横領が発覚したときの注意点

退職した従業員に横領の疑いが浮上したとしても、感情的な対応や法的知識のないままの行動は、があります。
そこでここからは退職後に横領が発覚したときに気をつけたい、以下3つのポイントを紹介します。
- 名誉棄損やプライバシー侵害にならないようにする
- 元従業員の私物への無断アクセスは違法になる
- 社内共有は慎重に行う
冷静でスマートな対処を行い、未然のトラブルリスクに備えましょう。
名誉棄損やプライバシー侵害にならないようにする

元従業員に対する対応を誤ると、名誉棄損やプライバシー侵害と見なされ、企業側が逆に法的責任を問われる可能性があります。
たとえば以下のような行為は名誉棄損やプライバシー侵害とみなされやすいです。
- 証拠が不十分な段階で社内に実名を共有
- チャットや掲示板で疑惑の言及
- 退職者の住所・家族構成を社内で共有
- SNSでの告発的投稿
特に昨今のSNSでは、情報を拡散して、不正をした人を晒し上げるという行為も散見されます。
不正への対応は、事実と証拠に基づいて冷静に判断し、社内外への発信は必ず法務担当や弁護士に相談の上で行うことが不可欠です。
感情的な拡散や不適切な言及は控え、法的に安全な範囲での行動を徹底しましょう。
元従業員の私物への無断アクセスは違法になる

退職後に元従業員のロッカーや私物に勝手にアクセスする行為は、不法侵入や窃盗などの違法行為に該当する可能性があります。
会社に保管されていたとしても、元従業員の私物であれば所有権は本人にあります。
本人の同意なく私物のカバンやスマホ、USBメモリの中身を確認した場合、不正アクセス禁止法などに問われる可能性も否めません。
元従業員の所持品に何らかの証拠が含まれていると疑われる場合でも、まずは弁護士に相談し、適法な手段での対応を検討しましょう。
社内共有は慎重に行う

元従業員に関する疑いを社内で共有する際も、共有範囲や表現方法に細心の注意を払う必要があります。
横領のような重大な不正が疑われると、社内では噂や動揺が広がりやすくなります。
無用な拡散や憶測によって、企業イメージやほかの従業員の信頼にも悪影響を及ぼしかねません。
また「金庫の件は○○さんの仕業かもしれない」という言葉がメールやチャットで広がれば、職場トラブルの原因になりますし、場合によっては従業員の一人がSNSなどで「横領があった」などと騒ぎ立てて、ネット上で騒ぎになる可能性も考えられます。
そのため、情報は必要最低限の関係者に限定して共有し、正式な文書・報告ルートで伝えることが重要です。
退職後に横領が発覚したときの証拠集めは探偵が最適

元従業員による横領が退職後に判明した場合、企業内部だけでの調査には限界があります。
そこで活用したいのが、証拠収集のプロである探偵です。
探偵がなぜ横領調査に適しているのか、3つの観点から解説します。
企業側だけでは把握できない情報も調査できる

探偵は企業では追えない範囲の情報まで調査できます。
退職後の従業員はすでに社内ネットワークの外にいるため、現在の職場での勤務中の様子や持ち出した物品、関係者との接触などを企業側で追跡することは困難です。
たとえば「社内資産が退職後にネットオークションで出品されていた」「他の従業員が横領の手伝いをしていた疑いがある」といった場合でも、探偵が張り込み・聞き取り・ネット調査などで情報を補完できることもあります。
企業内部の記録だけで調査が行き詰まっているなら、一度探偵に相談し、視野を広げた外部調査を依頼することが大切です。
警察や弁護士が動くための証拠の土台を作れる
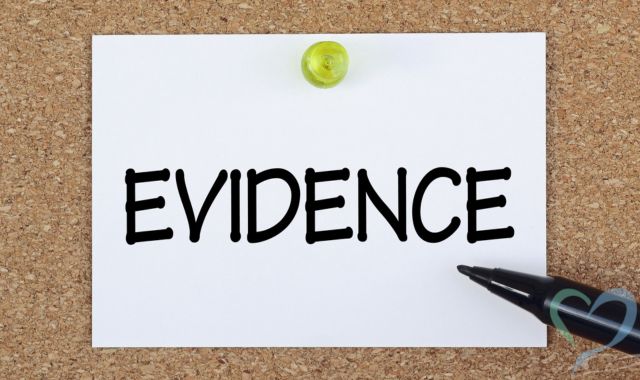
探偵は、警察や弁護士が法的対応を行うために必要な「一次証拠」を集める役割を担えます。
民事・刑事問わず、捜査や訴訟を進めるためには事実を裏付ける客観的証拠が不可欠です。
しかし、企業が収集した情報だけでは、証拠能力が不足して対応を断られることも少なくありません。
繰り返しになりますが、状況証拠だけでは警察や弁護士は動いてくれず、法的な手続きも行えません。
探偵に依頼すれば、たとえば「金庫の現金が消えたが、映像がなく犯人が特定できない」という場合、探偵が聞き取りや外部証拠の発見を通じて、行動の一貫性やほかの不正の証拠を補強できます。
結果として、警察が正式に捜査へ乗り出せる体制、弁護士が法的手続きを行なえる体制を整えられます。
合法な範囲で証拠を集めてくれる

証拠を自力で集めようとすると、プライバシー侵害や不正アクセスなど違法な手段に触れてしまうリスクがありますが、探偵は調査業におけるルールと法律の知識に基づき、許容される範囲で行動します。
たとえば、退職者の自宅を張り込む、関係者に聞き取り調査を行う、SNSで公開された情報を分析するといった方法も、法的に認められる範囲で慎重に行われます。
違法な調査で証拠が無効になってしまわないよう、はじめから探偵に依頼して、法的に使える証拠を確実に集めておきましょう。
退職後の横領発覚時に探偵が行う調査内容

探偵というと「不倫や調査」「尾行や張り込みを行う」というイメージが強く、退職後の横領でどのような役に立ってくれるのか想像が付かない人もいるかと思います。
退職後の横領発覚時に探偵が行える調査内容についてもチェックして、探偵に依頼するべきなのかの判断材料にしてください。
加害者の現住所・勤務先の調査

探偵は退職者の現住所や新しい勤務先など、現在の所在を調査できます。
加害者に損害賠償請求などの法的手続きを行うには、正確な住所や連絡先が不可欠ですが、退職後に連絡が取れなくなるケースも少なくありません。
たとえば退職後に引っ越して音信不通になっている場合、探偵が住民動向調査や張り込み・聞き込み調査などを行い、現在の居住地や職場を特定できます。
加害者の所在が不明で対応できない場合は、早めに探偵に相談して、連絡手段の確保から着手することが重要です。
本人の行動記録・退職後の生活状況

探偵は退職者の行動記録を収集し、横領の痕跡や不自然な金銭の流れを把握できます。
横領によるお金がどのように使用されているか、また浪費傾向や転売行為などがあれば、それが横領の裏付けとなる補助証拠になります。
たとえば、急に高価な買い物をしていたり、過去の社内物品が第三者に転売されているなどの事実が確認されれば、警察や弁護士が捜査・訴訟に着手しやすくなります。
横領の金銭の流れが不明な場合は、退職後の生活状況を含めて探偵に調査を依頼し、全体像をつかむことが鍵です。
内部協力者や証言者の調査

探偵は、元従業員の不正に関与していた協力者や、事件に関する証言者の存在を洗い出すことが可能です。
横領は単独犯ではなく、他の従業員が関与していたり、黙認していたケースも多くあります。
探偵が元同僚や関係者に聞き取り調査を行うことで、「○○さんが現金を持ち帰るのを見た」「○○さんが協力していた」などの証言が得られ、社内調査では届かない証拠が浮上することもあります。
社内調査で限界を感じている場合は、探偵に内部関係者の証言や動きを調査してもらい、横領の実態を立証していきましょう。
退職後の横領発覚時によくある質問

最後に退職後の横領発覚時によくある質問に答えていきます。
疑問点はここで解消して、スムーズな解決を目指しましょう。
横領の証拠が不十分な段階で本人に連絡しても良い?

原則としておすすめはしません。
証拠が不十分なまま連絡すると、証拠隠滅をされたり、逆に名誉棄損・脅迫などと取られるリスクがあります。
事実確認をしたい場合でも「疑っている」と明言するのではなく、冷静かつ客観的な確認を行うべきです。
不安があれば、弁護士や探偵に事前に相談してから対応するのが安全です。
退職金から横領分を差し引いても良い?
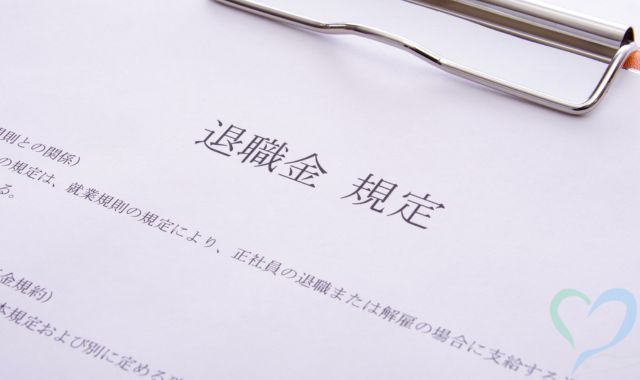
原則として本人の同意がなければ不可です。
未払いの退職金から損害分を一方的に控除することは「賃金の全額払いの原則」(労働基準法24条)に反する可能性があります。
損害賠償請求を行ったうえで、合意書を取り交わして相殺するか、法的手続きで差し押さえるのが基本です。
社内への共有や通達はどのように行う?

内容と範囲は特に慎重に考えてください。
横領発覚を社内で共有する際、対象者の実名や詳細を広く共有すると、名誉棄損やプライバシー侵害に該当する恐れがあります。
再発防止策として共有するなら「不正防止に関する通達」として抽象的に伝え、個人情報は極力伏せるのが基本と考えましょう。
横領の時効期間はどのくらい?

民事請求は原則3年です。具体的には、不法行為に基づく損害賠償請求は「加害者を知ってから3年」と決まっています。
なお、仮に加害者を知らなかったとしても、行為発生から20年が経過すると時効になります。
刑事告訴の場合は「業務上横領罪」に関しては7年が時効です。刑事の時効は「犯罪行為が終了した日」から起算されます。
退職後の横領の証拠集めはファミリー調査事務所にお任せください

退職後の横領は、時間が経つほど証拠集めが困難になってきます。
また、退職後だと元従業員の住所が変わっており、連絡がとれないケースも少なくありません。
そのため、退職後の横領の証拠集めで悩んでいるなら、探偵への依頼がおすすめです。
ファミリー調査事務所では、法人向けのサービスも行なっており、社内不正調査実績も多数あります。
ぜひ一度ご連絡いただき、横領の解決を目指しましょう。
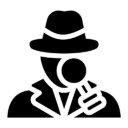
執筆者:米良
長年の情報収集経験を有し、英語での情報分析も得意とする。豊富な海外調査実績をもとに、国内外の問題を独自の視点で解説します。