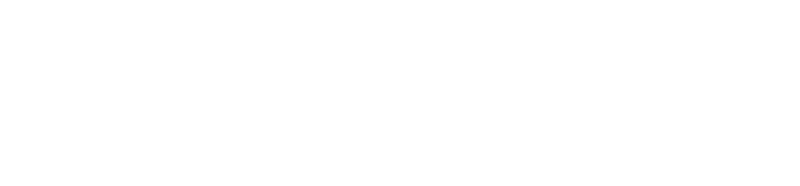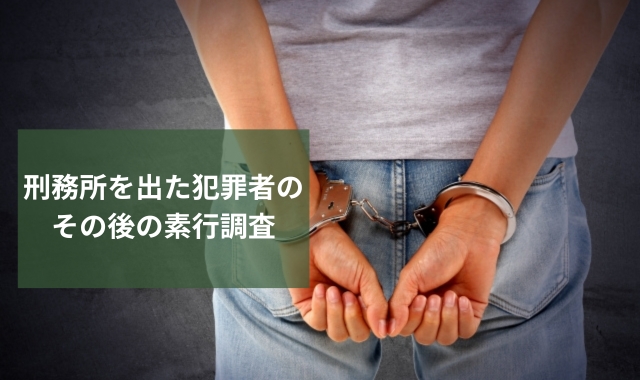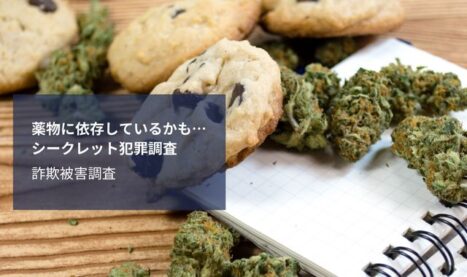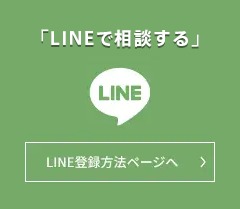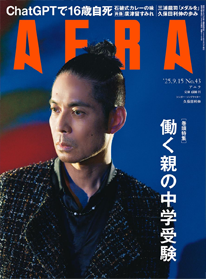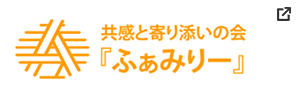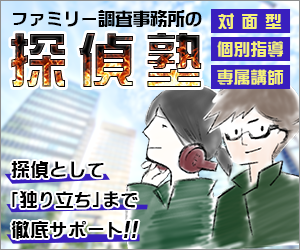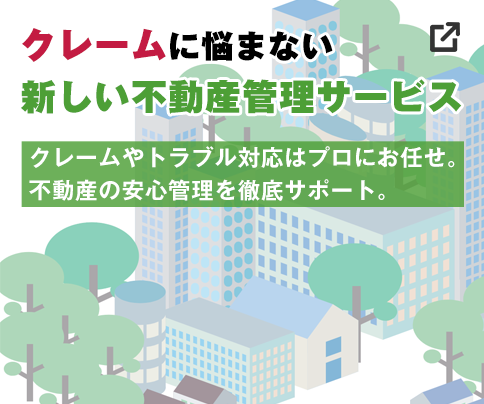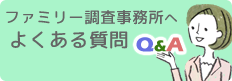被害者を守る仕組みは、裁判まで。その後、加害者がどこで暮らし、再犯リスクはあるのか…不安を感じる方は少なくありません。
出所後の生活や更生の実態を確認する方法について解説します。
目次
再犯率約60%|出所後に待ち受ける現実とは
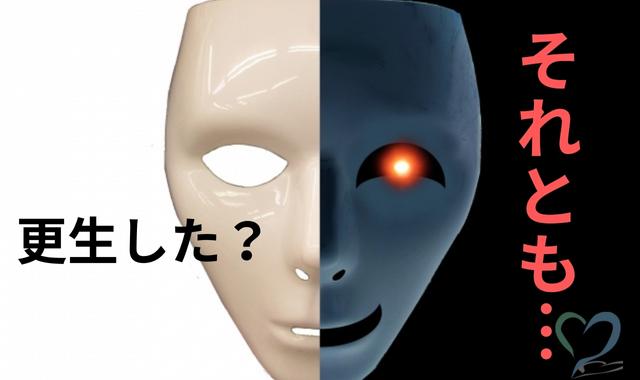
年間でおよそ3万人が刑務所を出所。そのうち仮釈放が約1万6千人、満期出所が約1万4千人です。
しかし、5年以内に再犯して戻る人は約6割という、深刻な現実があります。
出所後の住まいも安定せず、約44%が「行き先不明」とされ、社会とのつながりが断たれています。
また、有資格者でも刑罰歴によっては資格の効力が失われるなど、就労への壁も多く存在します。
これらの要因が、再犯リスクの背景になっていると考えられています。
前歴を隠して生きる人たち
過去を知られることで差別や拒否を受けるため、多くの出所者は前歴を隠して生活しています。
親族に受け入れてもらえず、保証人がいないことでアパートも借りられず、住居がないことで生活保護も受けられない人もいます。
更生への道をふさぐ社会の目
罪を償った後も、社会は彼らに厳しく、働く場を与えないことで孤立を深めています。
再犯すれば新たな被害者が生まれる可能性もあり、社会全体の課題といえます。
更生の意志があっても、支援や理解がなければ自立は困難です。見過ごせない現実です。
法制度のギャップと社会の課題
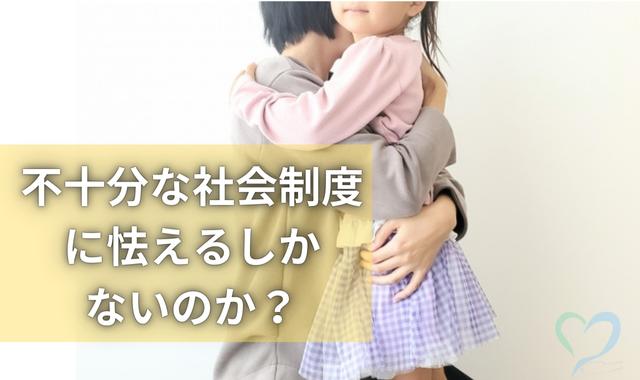
元受刑者の約6割が再犯している現状では、被害の連鎖を断ち切ることが難しくなっています。
もちろん、真面目に更生し社会復帰を目指す人もいますが、再犯防止の仕組みがまだ不十分です。
政府は対策の一つとして、性犯罪者へのGPS装着義務を検討中です。米国や韓国ではすでに導入され、韓国では再犯率の低下が確認されています。
ただし、GPSはプライバシーや人権問題も伴い、日本ではまだ導入には至っていません。
こうした制度の遅れや、元受刑者への社会的な偏見が重なることで、再犯リスクは今も高いままです。
ストーカー問題と安全対策の限界
「被害者通知制度」の役割と限界
ストーカーやDVの加害者が出所する際、被害者が事前に通知を受け取れる「被害者通知制度」があります。
出所情報を知ることで、加害者との接触を避けやすくなりますが、制度には限界があります。
たとえば、加害者が曖昧な地域名しか申告しなかった場合、実際の居場所が分からないこともあります。
さらに、制度がどれほど確実に機能しているかも疑問視される点があります。
被害は本人だけにとどまらない
ストーカー被害は、本人だけでなく家族や子どもにも影響が及ぶおそれがあります。
制度の不備を前提に、自分と家族を守る行動が求められます。
犯罪の種類別|再犯率の高いケースとは?

再犯率はすべての犯罪で同じではありません。特に再犯が多いとされる犯罪には傾向があります。
再犯率が高い犯罪の例
- 窃盗・万引きなどの財産犯:再犯率が最も高く、約70%に達するケースもあります。
- 薬物関連犯罪:覚醒剤や大麻などの薬物事犯も再犯率が高く、依存の問題が背景にあります。
- 暴行・傷害:衝動性や生活困窮に起因し、再犯に至るケースがあります。
- 性犯罪:再犯率は他の犯罪よりは低めとされる一方、社会的影響が大きく、再発防止の仕組みが重要です。
再犯の背景には、依存症、孤立、就労困難、偏見など複合的な課題があり、個別対応が必要とされています。
数字で見る再犯傾向(参考)
| 犯罪種別 | おおよその再犯率 |
|---|---|
| 窃盗・万引き | 約70% |
| 薬物犯罪(覚醒剤等) | 約50~60% |
| 暴行・傷害 | 約40% |
| 性犯罪 | 約10~20% |
※数値は法務省の資料や判例などをもとにした概算です。時期や調査によって前後することがあります。
軽微な犯罪でも前科に|処分の種類と執行猶予とは

犯罪の重さで変わる処分内容
犯罪には軽いものから重いものまでさまざまありますが、受ける処分も内容によって変わります。
主な刑罰には懲役・禁錮・拘留・死刑などがあります。
懲役は刑務所で作業をさせる刑罰で、有期(最短1ヶ月〜最長30年)と無期があります。
禁錮も拘束されますが、作業はありません。
執行猶予とは?
有罪になっても、刑の執行が猶予されることを「執行猶予」といいます。
3年以下の懲役・禁錮や、50万円以下の罰金刑に対してつくことがあります。
たとえば殺人罪でも、条件によって刑が軽くなり、執行猶予が認められるケースもあります。
不起訴や罰金刑もある
示談成立や証拠不十分などの理由で、検察が起訴しない場合もあります(不起訴処分)。
また、罰金刑だけで終わるケースもあります。
ただし、執行猶予付きの判決も有罪=前科がつくという点は変わりません。
このように、処分の重さに関係なく「前科」は記録されることを理解しておく必要があります。
次の章では、こうした処分を受けた人が再び犯罪を犯すリスク(再犯率)について解説します。
犯罪者の“その後”が不安…更生制度の限界と確認方法
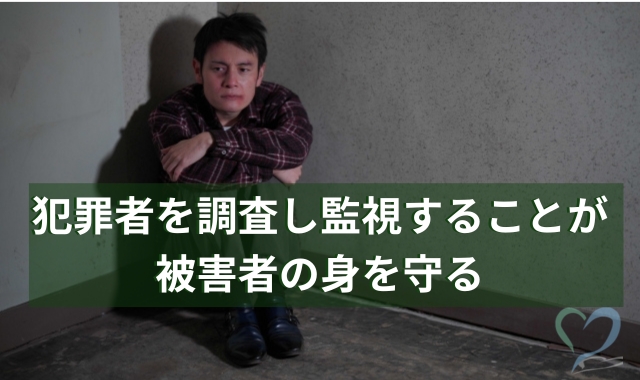
更生保護制度の問題点
現在の更生保護制度にはいくつかの欠点があります。
保護観察官や保護司の人手不足、再犯防止への対策不足などが指摘されています。
加害者の動向を知る方法
加害者の出所情報を得たい場合は、法務省の「被害者等通知制度」を活用するのが基本です。
さらに詳しく知りたい場合、探偵や調査会社への依頼も選択肢の一つです。
自分で追うのは危険
注意が必要なのは、被害者自身が加害者を追いかけるのは非常に危険だということです。
万が一、本人に見つかれば再びトラブルが起こるリスクがあります。
次のセクションでは、「なぜ加害者のその後が気になるのか」という被害者の心情についてご紹介します。
なぜ犯罪者のその後を知りたいのか? 被害者の心の声

被害者や家族の心にあるもの
被害者の心情
加害者の“その後”が気になる背景には、心の整理や安心を得たいという気持ちがあります。
訴訟が終わっても、被害者にとっては終わりではないのです。
犯罪者の反省は本物か?
本当に反省しているのか。新たな被害を起こさないか。
そうした確認のために、加害者の今を知りたいと思うのは自然な心の動きです。
終わらない不安
「また会ったらどうしよう」そんな思いを抱えながら日常を送る人もいます。
加害者の現在地や行動を知ることで、少しでも安心を得たいという方も少なくありません。
調査によって得られる情報は、被害者の心の支えになることもあります。
探偵による調査の実際
探偵は、犯罪者の現在の暮らしや行動を調査するための知識と技術を持っています。
依頼者の目的を確認した上で、適法な範囲で慎重に調査を進めます。
素行調査
対象者の現在の生活パターンや交友関係を調査します。
尾行・張り込み
実際の行動を確認し、生活状況を記録・報告します。
情報収集
関係者や地域の口コミから、対象の行動傾向を探ります。
加害者の「今」を知ることは、被害者にとって大切な一歩となることもあります。
出所者による“再接近”トラブルの実例

出所後に再犯するケースは少なくありません。特に「元被害者に再接近する行為」は、深刻な二次被害につながるおそれがあります。
実際にあった出所者の再接近トラブル
例①|SNSで「久しぶり」とメッセージが届く
性犯罪で有罪となった加害者が出所後、被害者のSNSを探し出し「また会いたい」と連絡。恐怖で被害者が再び心療内科に通う事態に。
例②|職場に突然現れた元加害者
過去の暴力事件の加害者が、出所後に被害者の職場を突き止めて来訪。特に接触は禁止されていなかったため、法的対応に苦慮したという例も。
例③|自宅近くをうろつく不審者がまさかの出所者
嫌がらせ被害の加害者が出所後、被害者宅の周囲をうろつく姿が防犯カメラに映る。警察に相談するも「直接的な接触がない」と対応が難航。
このように、「再犯」だけでなく「再接近」そのものが被害者にとって大きな恐怖となります。
判決や刑の執行が終わっても、被害者にとっては「本当の終わり」ではありません。
事前の対策が安心を守る
不安がある場合は、出所後の行動を把握できるようにすることが重要です。
探偵による身辺調査や接近防止対策の相談も、一つの方法です。
見えない不安や身を守るために

「あの人がまた現れるかもしれない…」「本当に更生しているのか…」
そんな見えない不安に押しつぶされそうなとき、
調査によって“安心”という答えが得られることもあります。
ファミリー調査事務所では、元加害者に関する調査や、再接近の可能性に備えたリスクチェックを行っています。
専門の相談員が、ご依頼の目的や不安を丁寧にヒアリングし、必要に応じた対策をご提案します。
また、調査後も、心のケアや生活面のフォローアップを行い、安心して前を向ける環境づくりをサポートします。
どんな小さな悩みでも、あなた一人ではありません。まずは、話すことからはじめてみませんか。
⚠ 復讐目的のご依頼はお断りしています
加害者への復讐を目的とした調査は、法的に問題があるだけでなく、さらなるトラブルを引き起こす可能性があります。
私たちは、依頼者が安心して日常を取り戻すための支援を目的とした調査のみをお受けしています。
まずは、お気軽にご相談ください。
あなたの不安に、私たちが寄り添います。
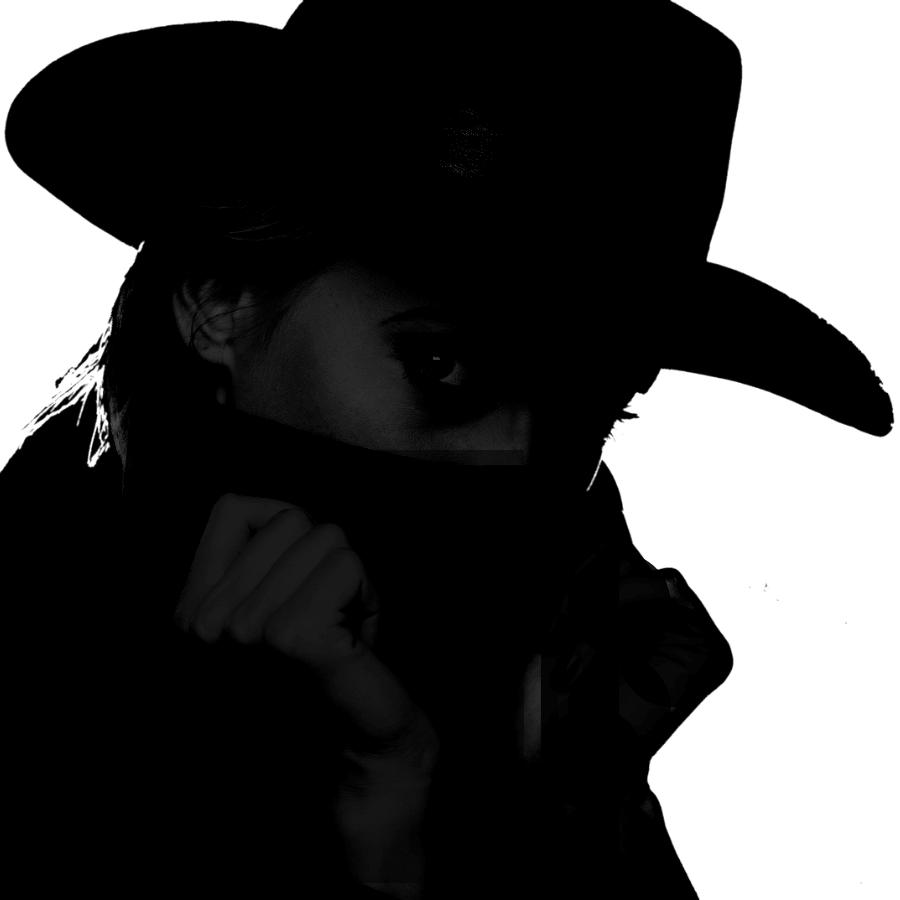
執筆者:Maiko Yoshida
男女トラブルカウンセリング歴10年以上。男女トラブルの問題解決を得意とする。調査も多数兼任・実績あり。依頼者に寄り添ったサポートが定評。