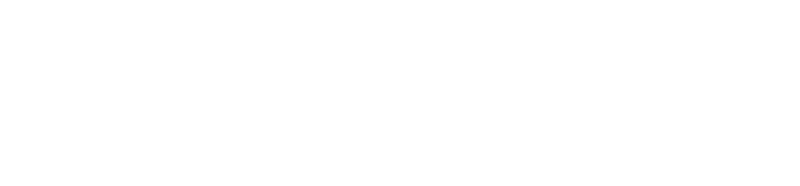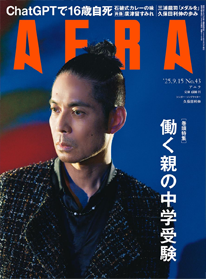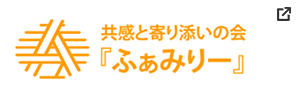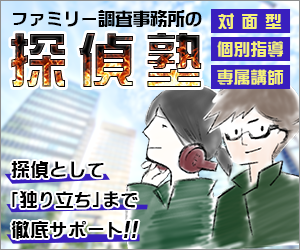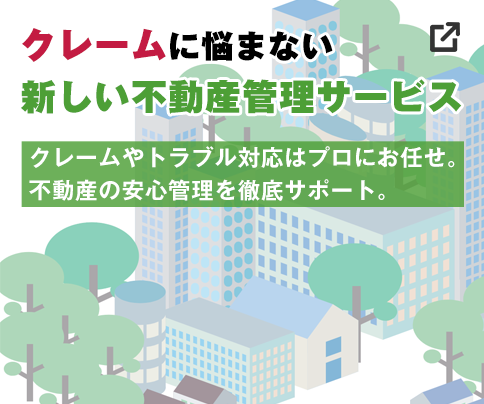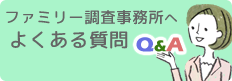「ネットの風評被害がひどい」
「どうやって対処するべきか分からない…」
ネット上の誹謗中傷や根拠のない噂によって、生活や仕事に深刻な影響を受けるケースは少なくありません。
いわれのない噂でネット上での立場を失ったり、職場や家庭にまで被害が及ぶこともあります。
そこで本記事では、ネット風評被害に悩む個人が取るべき具体的な対策を解説します。
自分でできる対応から、探偵や弁護士などの専門家に任せるべき領域なども解説しました。
根拠のない情報拡散、風評被害に対して冷静かつ的確に対応するために、正しい知識と手段を確認しておきましょう。
目次
ネットの風評被害を対策すべき理由

ネット上では数多くの人が情報を発信しています。特にSNSでは情報がシェアされる機会が多く、あっという間に広がっていきます。
ネットの噂も、最初は「ただのよくある嘘」「誰も信じない」と思って放置していても、シェアされて拡散されていくと、状況が変わることも少なくありません。
対策しないと、以下のようなリスクが発生するため、放置をせずに対処を心がけましょう。
退職や休職を迫られる

ネット上に個人の誹謗中傷や虚偽情報が出回ると、職場での立場に影響が及ぶ場合があります。
たとえ内容が事実と異なっていても、周囲が疑念を抱けば、本人への接し方が変わることは珍しくありません。
特に、実名や勤務先が特定されているケースでは、社外からの問い合わせや社内の評判悪化を招きやすく、次第に働きにくい環境へと変化していきます。
結果として、心身の負担が大きくなり、自主的に退職や休職を選ばざるを得なくなることもあります。
職場にて取引先や顧客からの信頼を失う

ネット上に勤務先とともに誹謗中傷が広がると、企業の信用にも影響を及ぼすことがあります。
従業員一人ひとりの言動や印象が、会社全体の評価に結びつくことはごく自然です。
書き込まれた内容が事実ではない場合でも、「適切な管理がなされていないのではないか」といった懸念を抱かれる可能性は否定できません。
その結果、職場にて取引先や顧客からの信頼を失い、契約の再検討や取引停止といった判断が下されることもあります。
家族や友人に距離を置かれる

ネット上で拡散された風評は、家族や友人など親しい関係にも影響を及ぼすことがあります。
特に実名が含まれている場合、検索結果やSNSを通じて、周囲の人の目に留まりやすくなります。
本人にとっては根拠のない情報であっても、第三者には真偽の判断がつかないことがほとんどです。
そのため、不安や混乱から、関係を控える選択を取られるケースもあります。
ネット風評被害事例

では、実際にどのようなネット風評被害事例が発生しているのか、見ていきましょう。
これらは深刻な事例ではありますが、どれも個人に対して発生したもので、どんな人でも起こり得ます。
事例①:殺人事件の犯人であるというデマがネットで拡散

とある凶悪な殺人事件の犯人が男性テレビタレントであるとして、ネットで噂が広まっていった事例があります。
そのテレビタレントは事件とは全くの無関係であるにも関わらず、このような噂が広まってしまったため、男性は数多くの誹謗中傷被害を受けました。
さらに男性の恋人や親族、男性が所属している事務所などにも影響が出ました。
結果として、誹謗中傷を行った複数の被疑者が一斉摘発されるまでの事態となっています。
事例②:無関係の男性が「加害者の父親」と誤認されネットで拡散
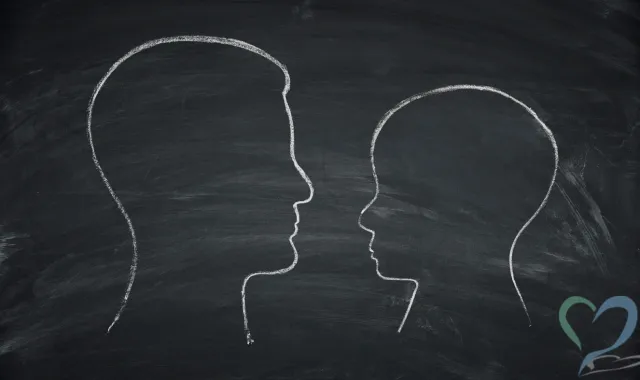
全くの無関係の一般人男性が、とある事件の加害者の父親と誤解されネットに晒された事件もあります。
こちらは比較的最近の事例で、YouTuberが再生数を稼ぐために根拠がないのにも関わらず動画撮影をし、ネットにアップしたことが元の原因となっています。
これによって、いたずら電話がかかってきたり、家の近くを見慣れないナンバーの車が来たりするなどの被害に遭いました。
一般人でもこのように思わぬネット風評被害に遭うケースがあることは留意しておかなければいけません。
事例③:VTuberがネット風評被害を受け活動に支障

VTuberがネット風評被害を受けて、活動に支障をきたしてしまっているケースもあります。
近年ではネットで情報の拡散スピードは非常に早く、特にVTuberのようなネットでの活動を基本としている人は、風評被害を受けやすいです。
普段からSNSを使って活動している人は、より一層ネット風評被害に対する意識を高く持つ必要があります。
ネットの風評被害を最小限に抑えるために大事なこと

ネットの風評被害を受けたら、そのあとはすぐに情報が拡散されていきます。
早めに対策して被害を最小限に抑えるためにも、以下のポイントを理解しておきましょう。
証拠を確保する
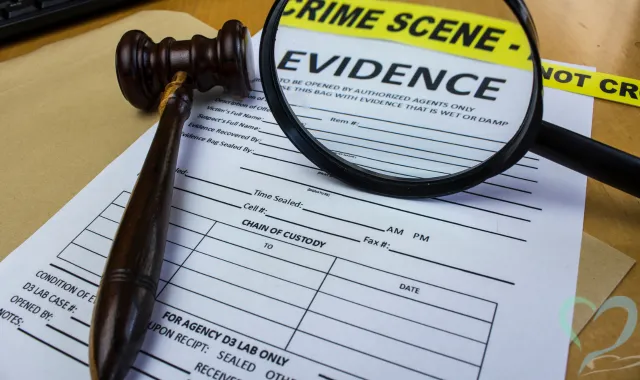
ネット上で風評被害を受けた場合、まず最初に行うべきなのが証拠の確保です。
投稿が削除されたり、アカウントが非公開になる前に、次の情報を証拠として残しておきましょう。
- 投稿画面のスクリーンショット
- 投稿日時
- URL
- 投稿者のアカウント名
ツールによっては、画面全体を日時付きで保存できるサービスもあるため、必要に応じて活用してください。
こうした情報は、後に投稿者を特定したり、削除や損害賠償を求めたりする際に、正確な事実関係を示す材料になります。
可能な限り早い段階で客観的に記録しておくことが、対策の第一歩です。
個人情報の追加流出を防ぐ

風評被害が発生した際には、それ以上に被害を広げないための対応も重要です。
特に注意すべきなのは、ネット上に公開されている個人情報がさらに拡散されたり、別の情報と結び付けられたりするリスクです。
特に以下のような情報は、攻撃の材料として悪用されるリスクがあります。
- 氏名
- 勤務先
- 連絡先
- 顔写真
- SNSやブログのプロフィール欄の記載内容
すでに公開されている内容であっても、被害が拡大する局面では見直しが必要です。
設定を非公開に切り替える、不要な投稿を削除するなど、現在の発信状況を一度点検して、リスクを抑えましょう。
冷静さを保つ

ネット上で誹謗中傷や虚偽の情報を受けたとき、強い不安や怒りを感じるのはなにもおかしくはありません。
しかし、感情的に反応してしまうと、状況をさらに悪化させる可能性があります。
投稿に対して直接反論したり、過剰に反応したりすると、新たなトラブルや誤解を招くこともあります。
まずは状況を客観的に整理し、何が書かれているのか、どこまでが事実でどこからが誤情報かを冷静に把握することが大切です。
自分でできる対応と専門家に任せるべきこと

風評被害が発生したら、さまざまな対策・対処をする必要があります。
しかし、そんな中でも、自分でできるものと専門家に任せるべきものがあります。
それぞれをチェックして、よりスムーズな対応ができるようにしましょう。
個人でできる初期対応

ネット風評被害が発生したら、即座に専門家に任せるのがベターですが、依頼する前の段階で、本人が行える対応もいくつかあります。
個人でできる主な対応は以下のとおりです。
- 問題となっている投稿のスクリーンショットを保存する
- 書き込みのURLや投稿日時、アカウント情報などを記録する
- SNSやブログの公開設定を見直す
- 状況をメモや時系列でまとめておく
こうした対応を初期段階で行うことで、後から専門家へ相談する際にスムーズな対応をしてもらえます。
探偵による投稿者特定と証拠収集

投稿者の特定や証拠の整理は、探偵が得意とする分野です。
匿名の書き込みでも、調査によって発信元にたどり着ける場合があります。
探偵が対応できる主な業務は以下のとおりです。
- 掲示板やSNSへの投稿履歴の調査
- 関連アカウントの特定と行動記録の整理
- 時系列や関連性を整理した証拠資料の作成
- 弁護士との連携を前提とした事前調査
これらの情報は、削除請求や損害賠償を行うための下準備になります。
投稿内容が事実かどうかに関わらず、証拠の確保は欠かせません。
弁護士による削除請求と損害賠償請求

投稿の削除や損害賠償を正式に求めるには、弁護士による法的手続きが必要になります。
これらは個人では対応が難しい場面も多いため、弁護士に任せるのが確実です。
弁護士ができることは以下のとおりです。
- プロバイダへの発信者情報開示請求
- 投稿者への損害賠償請求
- 内容証明郵便による通知や交渉
- 訴訟を含む一連の法的手続き
探偵が集めた証拠と連携することで、より正確かつ強力な対応が可能になります。
請求に向けた準備が整っていれば、弁護士側でもスムーズに手続きを進められるでしょう。
ネット風評被害の対処で探偵事務所を選ぶときに見るべきポイント
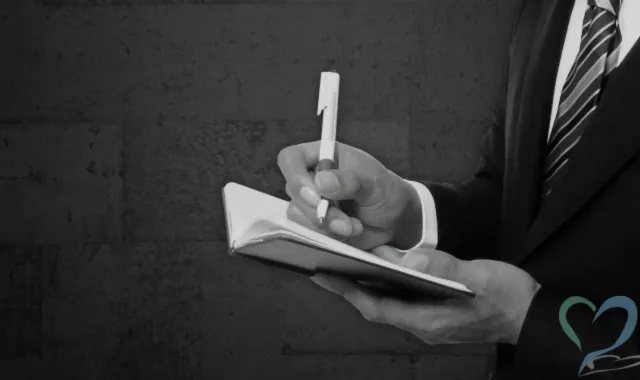
前述のように、ネット風評被害を対処するには探偵への依頼は欠かせません。
しかし、探偵へ依頼するにしても、どのように事務所を選ぶべきなのか迷ってしまうことは多いです。
そこで、ネット風評被害の対処をする上での、探偵事務所選びで重視するべきポイントをまとめました。
料金体系

- 着手金
- 調査費
- 成功報酬
- 追加費用の有無・条件
探偵に調査を依頼する際、まず確認すべきなのは料金体系の明確さです。
ネット調査の費用は依頼内容や期間によって変わるため、事前の説明が不十分なまま契約すると、想定外の支出が発生するおそれがあります。
着手金、調査費、成功報酬といった各項目の内訳が明示されているか、追加費用が発生する条件が説明されているかなど、契約前に細かく確認しておくことが必要です。
電話相談や無料見積もりの段階で、費用について具体的に説明があるかも重要な判断材料となります。
料金に関するトラブルを避けるためにも、口頭の説明だけでなく、書面やメールなど記録に残る形で費用内容を確認できる環境を作っておきましょう。
ネット風評被害の対処実績

探偵事務所によって得意とする調査の分野は異なります。
浮気調査や人探しに強い事務所であっても、ネット上の風評被害に関する調査に精通しているとは限りません。
ネット風評被害では、匿名の投稿者特定やデジタル証拠の収集など、専門的な技術や知識が求められます。
実績がある事務所であれば、過去の対応例をもとに、適切な手順で調査を進めてもらえる可能性が高くなります。
依頼先を選ぶ際には、公式サイトや相談時のやり取りを通じて、ネット調査の経験があるか、どのような事案に対応してきたかを確認しておくことが重要です。
無料相談の有無

風評被害の対応には、状況に応じた判断が求められます。
探偵事務所によっては、せっかくお金をかけて相談したのに「このような事例は対応できない」と断られてしまうケースも少なくありません。
事前に無料相談を受けられる事務所であれば、費用をかけずに現状を整理し、対応の可否や方針を確認できます。
初回対応の内容

探偵事務所によって、相談から実際の調査に入るまでの流れには違いがあります。
初回対応の内容をあらかじめ確認しておくことで、調査の進め方や所要時間を把握しやすくなります。
たとえば、ヒアリングだけで終わる事務所もあれば、相談の段階で簡易調査や過去の類似事例をもとにした説明を行ってくれる場合もあります。
また、証拠の有無や調査の実現可能性を初期段階で判断してもらえるかも重要な要素です。
調査の方向性を早期に掴むためには、初回から具体的な対応をしてくれるかどうかを見ておくことが大切です。
連携している弁護士の有無

投稿者の特定や証拠の収集が完了しても、最終的な対応には法的手続きが必要になることがあります。
法的手続きをするには弁護士の力は必要不可欠なので、探偵事務所が弁護士と連携しているかどうかは必ずチェックしましょう。
調査結果をそのまま引き継いで削除請求や損害賠償請求ふぁ可能な体制が整っていれば、依頼者が改めて別の専門家を探す手間が省けます。
ネット風評被害に関するよくある質問


匿名の投稿でも対応できる?

対応できます。投稿に使われたIPアドレスなどの通信記録をもとに、投稿者を特定できる可能性があります。発信者情報開示請求などの法的手続きを通じて追跡が可能です。

証拠がないとどうなる?

削除請求や損害賠償請求が難しくなります。投稿が削除された後では事実関係を示せなくなるため、見つけた時点で記録を残すことが重要です。

削除請求と損害賠償請求の違いは?

削除請求は投稿の取り下げを目的とし、損害賠償請求は金銭による補償を求める手続きです。両方を同時に進めることも可能です。

費用はどのくらい必要?

対応内容によって異なります。調査のみを依頼する場合と、弁護士による法的手続きまで進める場合では、必要な費用も変わります。見積もりを事前に確認してください。

周囲にバレずに対応できる?

可能です。相談や調査、法的手続きは非公開で進められます。家族や職場に知られたくない場合は、最初にその旨を伝えておくと安心です。
ネット風評被害の対策はファミリー調査事務所にご相談ください

ネット上の誹謗中傷や風評被害は、放置すると私生活や仕事に深刻な影響を及ぼすことがあります。
早い段階で対応を始めることで、被害の拡大を防ぎ、状況を立て直すことが可能です。
ファミリー調査事務所では、投稿者の特定や証拠の収集に対応しており、必要に応じて弁護士と連携した法的手続きにもつなげることができます。
相談はLINEでも受け付けており、初回から状況に応じた適切な方針をご案内します。
一人で悩まず、まずは現在の状況についてぜひご相談ください。
ネット風評被害にも精通した専門スタッフが問題解決に向けた一歩をサポートいたします。
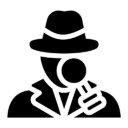
執筆者:米良
長年の情報収集経験を有し、英語での情報分析も得意とする。豊富な海外調査実績をもとに、国内外の問題を独自の視点で解説します。